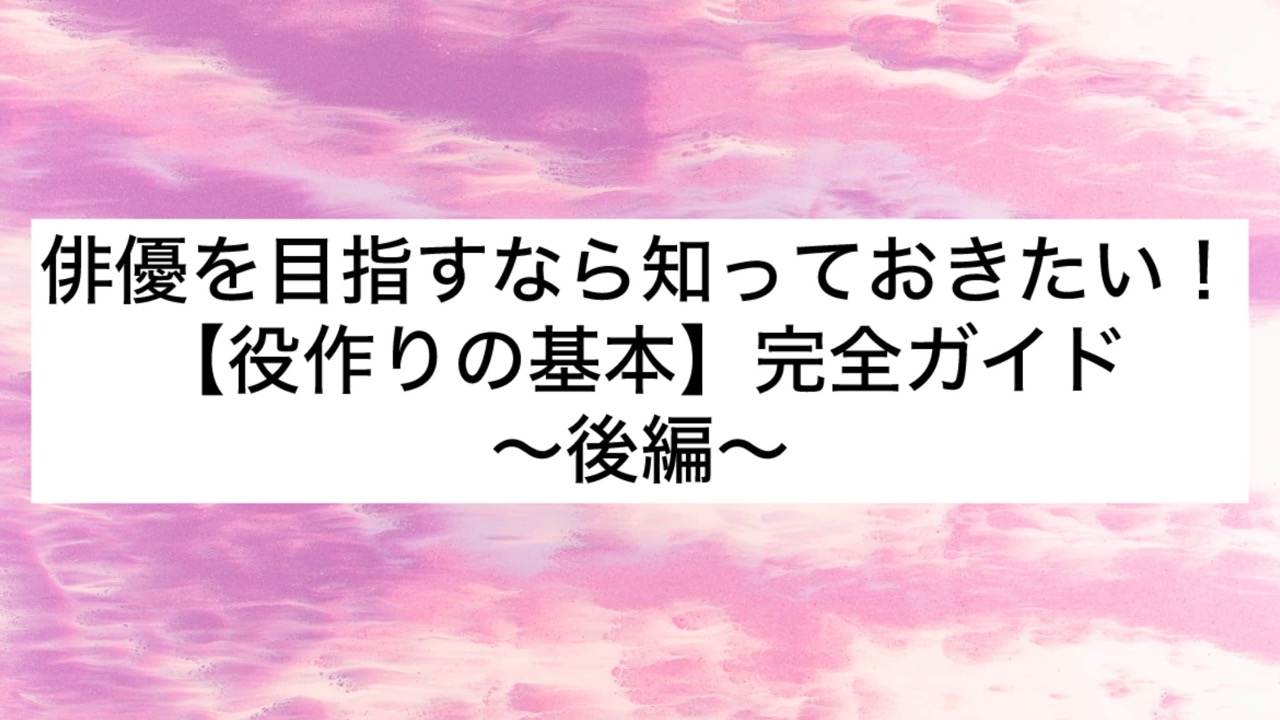演技・話し方講師の矢野衣千佳です。
前回のブログでは、役作りの基本として、
・台本に描かれている役のキャラクターを探す方法
・キャラクターに深みを出す考え方
をご紹介しました。
今回のブログでは、その次の段階である 「考えて作ったキャラクターを、どうやって自分の中に落とし込むか?」 をテーマにお話ししていきます。
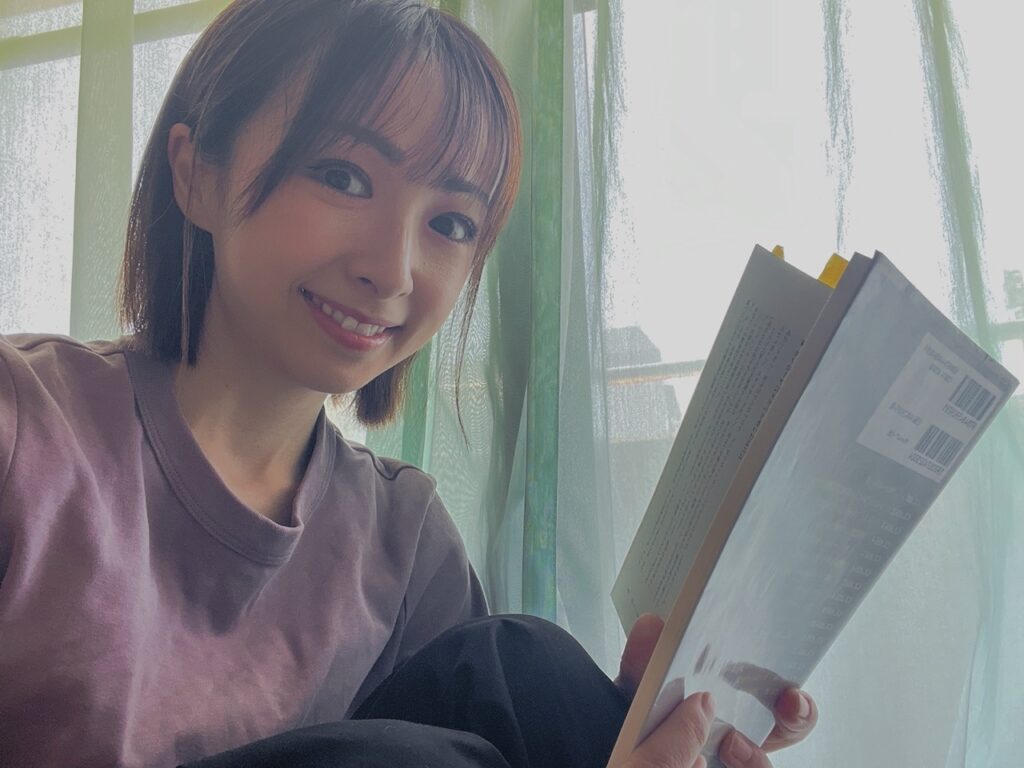
役の落とし込み方
例えば、与えられた役が「病気を患っている」という設定だったとしましょう。
仮に患っている病気が『リウマチ』だとします。
この設定を受け取ったら、まず最初にやるべきことはリサーチです。
「自分がその病気になってしまったとしたら?」という視点で、必死に調べてみてください。
・リウマチとはどんな病気?
・どんな病院に行くべき?個人病院で対応できる?総合病院?大学病院?何科を受診する?
・発症してからどのような段階を経て悪化するのか?
・自分の役は、発症からどのくらい経過している? (発症からの時間や、治療の有無・効果によって痛みの度合いも変化します)
・どんな治療を行っている?使っている薬は?副作用はある?
・治療開始までにどのくらいの期間がかかった?
・診断に至るまで、その役はどんな葛藤や不安を抱えていた?
・現在の病状は?痛みの程度は?痛む部位はどこ?
などです。
さらに、実際にその病気を患っている人の体験談を調べることも非常に大切です。
今はインターネットのおかげで、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)など、多くのSNSを通じてリアルな患者さんの声に触れることができます。
人によって症状の出方や苦しみ方も違うので、複数の情報に触れてみることが大切です。
実際に自分の中に落とし込む
リサーチが終わったら、次は自分の身体で感じてみましょう。
たとえば「右股関節の骨が破壊され、右足を地面につけると激痛が走る」という設定なら、実際に1日、右足を引きずって生活してみるのです。
電車移動の際には、階段を避けてエスカレーターやエレベーターを探すでしょう。
左足を主に使うため、すぐに疲れて座りたくなるかもしれません。
混雑した場所では、誰かにぶつかられたら転びそうになる恐怖も感じるでしょう。
このような体験を通じて、100%の理解は難しくても、『不自由さ』『もどかしさ』を実感することはできます。
そしてその体験を、演技の中に活かしていくのです。
・セリフのないシーンで、痛みに顔をゆがめる演技。
・足を引きずる動き。
・痛みに耐えながら椅子を探す様子。
・薬の副作用による吐き気を表現する。
これらは、役作りをしたからこそ出て来る演技で、リアリティがあります。
俳優の仕事は半分以上が準備
アカデミー賞やゴールデングローブ賞を受賞しているイギリスの俳優、エディ・レッドメインは、 映画「博士と彼女のセオリー」で、実在のALS患者ホーキング博士を演じました。
その際、彼は博士のインタビュー映像を何度も見返し、生活スタイルを研究するために半年を費やしたそうです。
この映画は、役作りに悩んでいる方にぜひ観ていただきたい作品です。
ホーキング博士を演じるエディの表現力は、アカデミー賞受賞も納得の素晴らしい演技で、 与えられた役に対するリスペクトと、どれだけの情熱・時間・労力を注いだかが強く伝わってきます。
最後に
役作りは、役を演じるうえで必ず必要なプロセスですが、 演技の基礎ができていなければ、頭で「こう演じたい!」と思っても、身体でそれをうまく表現することができません。
だからこそ、俳優は24時間、芝居のことを考えるのです。
レッスン以外でも、自分の人生の経験をすべて演技に活かすつもりで、 人の感情の動き、自分の感情の変化に敏感でいることが求められます。
また、身体も自由に使えるように、神経伝達のトレーニングも必要です。
演技は1日や2日で上達するものではありません。
たとえ現場に立つようになっても、学びは一生続きます。
一筋縄ではいかないからこそ、 それを楽しんで取り組んでいけることが、上達への近道です。