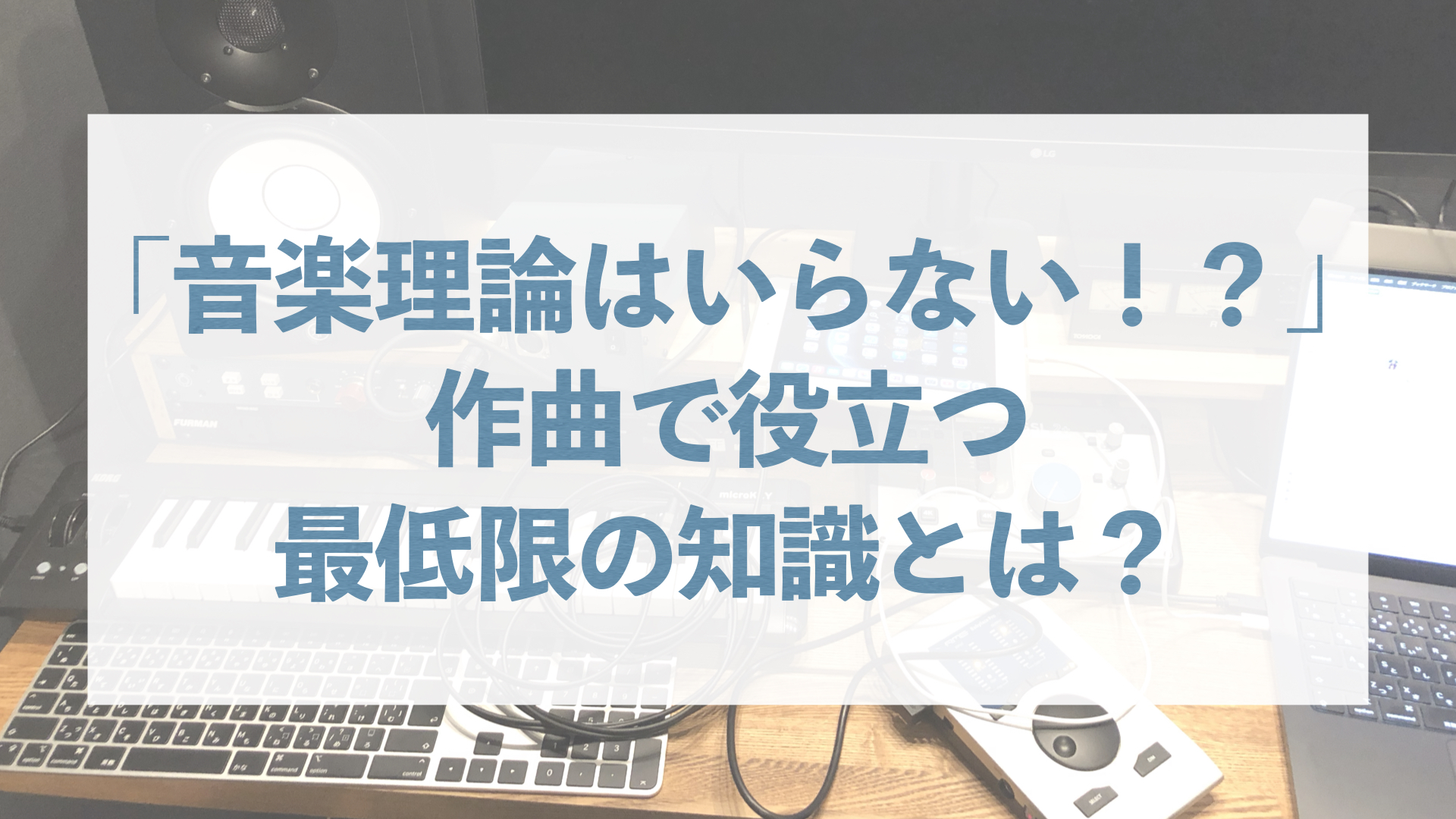どうも、WACCA MUSIC SCHOOL中澤です!
作曲界隈を見ているとたまにみかける「音楽理論なんていらない!感性がすべて!」というパワーワード。
たしかに理論ってむずかしそうだし、覚えるの大変そうだし、「作りたい曲は頭にあるんだよ!」って感じですよね、気持ちはめちゃくちゃわかります。
ただ知っていると便利なこともあるので、自分はいまから作曲がんばるぞ〜って人には「音楽理論はめんどいから別にいらないよ!ただ困ったときは助けてくれる地元のお兄ちゃんみたいな人だからたまに会っておくといいよ!」みたいなトーンで話しています。
ということで今回は、「感性重視派」なあなたにもぜひ知っておいてほしい「最低限ここだけは押さえておくと便利」という作曲における音楽理論の基礎を、初心者向けにゆるっと語っていきたいと思います。
知っておくと便利な理論3選
・スケール(音階)
「Cメジャースケール」や「Aマイナースケール」などですね。
これは使っていい音の範囲がわかる基礎で、コードやメロディの「迷子にならない地図」みたいなもの。
大体でいいので、「このコードに対して、この音ならハマる」くらいは知っておくと簡単な編曲でもDTMなどで自分でできるようになります。
・ダイアトニックコード
超ざっくり言えば、「そのキーで自然に使えるコードたち」。
CメジャーならC・Dm・Em・F・G・Am・Bdimってやつですね。
この知識があるだけで、なんとなく伴奏がつけられるようになります。
ただし転調に気をつけて。
・ペンタトニックスケール
難しそうな名前ですね。
これは「なんかいい感じのメロディになる5つの音」と覚えましょう。
さっき出てきたそれぞれのスケールの中できらめく5つの音です。
ギター・ソロなどでよく意識されますが歌のメロディを作るときに参考にする人もよくいます。

実際作曲するときには
最近作曲を本当にはじめてやった生徒さんのレッスンでは
サビのメロディの作成:本人の頭の中の音を書き起こす
↓
サビに合う伴奏を付ける:ダイアトニックコードを基本に、合うコードを探す
↓
AメロBメロ作成:サビのコード進行を流しながらAメロ、Bメロのメロディを思いつく
↓
完成!
みたいな流れでやりました。
大体アイデア出しの時間を入れて6〜7時間くらいでできました。

まとめ
どうですか?
感性や思いつきも大事ですが理論つまり地元のお兄ちゃんもいると、結構サクッと全体の曲を完成させることができたりします。
みなさんもうまく音楽理論と付き合ってよい作曲ライフを!