はじめまして!
WACCA MUSIC SCHOOL 講師の吉岡です。
今回は、作曲入門2!
今回は、作曲入門2!ということで、7thなどを含む4和音を取り扱っていきます。
キーの概念や3和音のダイアトニックコードについての解説は、前回ブログ「作曲入門 コード進行の作り方」を読んでみてください。
4和音とは?
コード譜などで、◯M7、◯m7、◯7 という記号を見たことはありますか?
これらのコードは、4音の構成音から作られているので、4和音といいます。
(パワーコードなどを除く)コードの最小単位は3音からでしたね。ド・ミ・ソでCになるといった感じです。
このCというコードの主音ドから数えて7番目の音を重ねると4和音になります。
音楽理論を考えるときには3和音ではなく、4和音で考えるのが基本となります。
4和音の種類
4和音には主に3種類 + 様々な応用型があります。
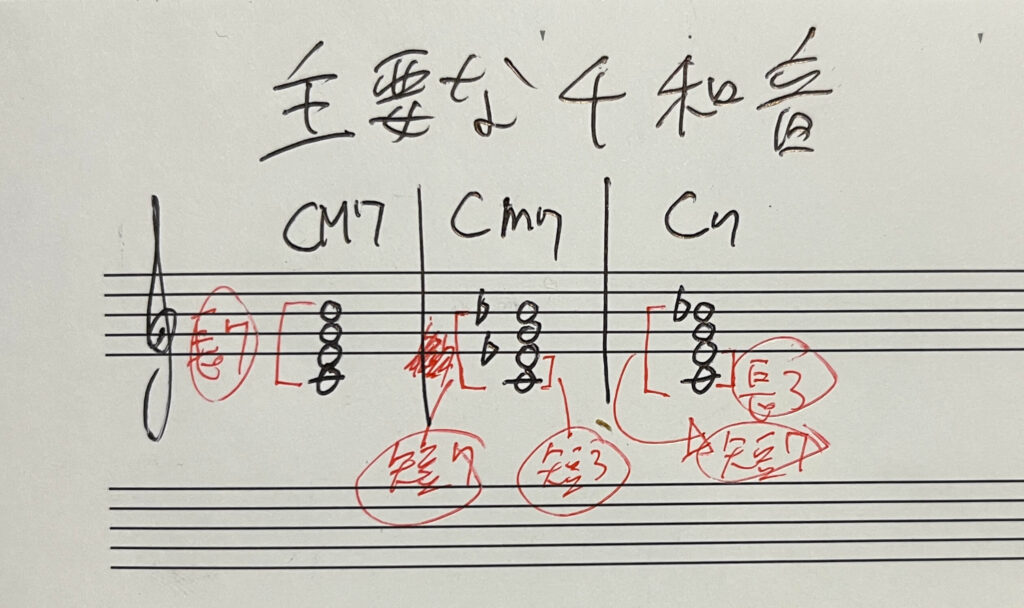
- ◯M7
- ◯m7
- ◯7
まず7度には、長短(メジャーM・マイナーm)があります。
半音10個離れていたらm7th、11個離れていたらM7thです。
CコードにM7thの音であるシの音を重ねるとCM7になり、Cmコードにm7thの音を重ねたらCm7になります。
そして、Cコードにm7thを重ねるとC7になります。
これらの違いをしっかりと理解してください。
ダイアトニックにおける4和音
前回の作曲入門で説明しましたダイアトニックコード。これらに7thをつけていきましょう。
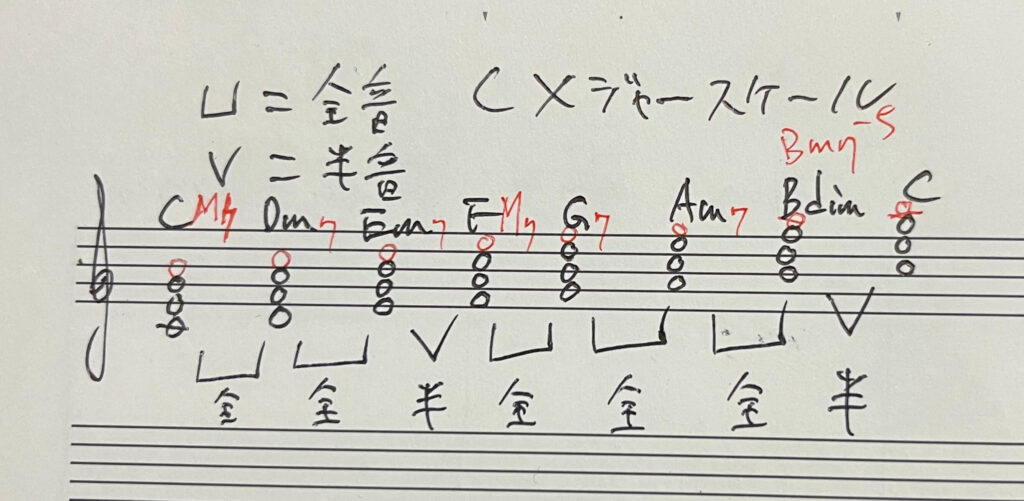
上記のような並びになります。
メジャーコードはM7。マイナーコードはm7になってますね。
ここで例外が二つ!!
5番目Gと7番目のBdimは少し違います。
5番目の和音はドミナント和音と言って、メジャーコードであるGにm7thを足し、G7になります。
ドミナントはトニックに向かうという特性があります。
(詳しいコードの機能については、次回解説したいと思います。)
そして、Bdimにm7が足され、Bm7-5 (B half dimとも言う) と表記されます。
dimとは第5音が半音下がったコードなので、このような表記になるのです。
7thのさまざまな変化
さて、ここまで頻出の4和音を解説してきました。
説明したもの以外にもたくさんの4和音が存在します。
しかし、ほとんどがこれら下記3つの応用になります。
- ◯M7
- m7
- 7
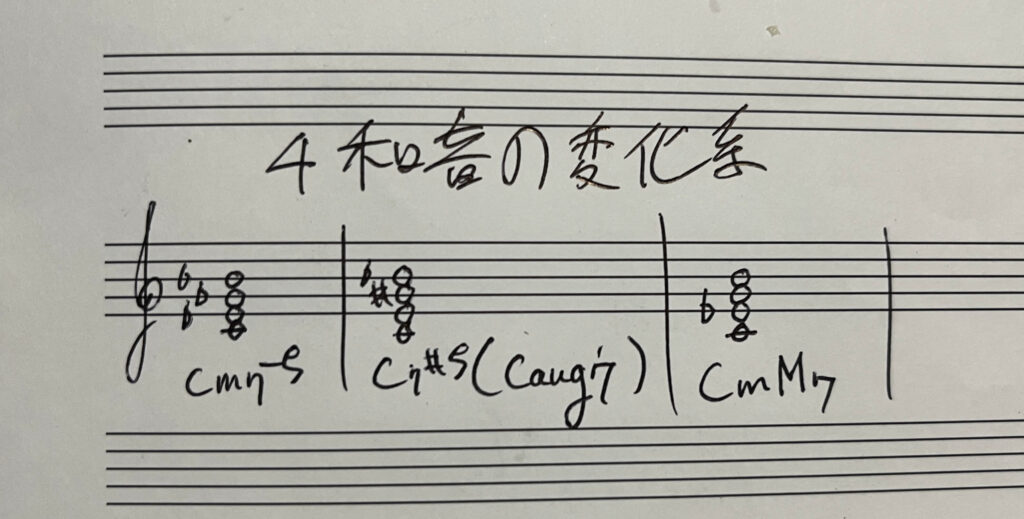
例えば、先ほど解説した◯m7-5など。
また、第5音が半音上がると#5(もしくはaug)という表記になります。C7#5 (Caug7)など。
登場頻度は高くないですが、◯mにM7thがつくと、◯mM7というコードになります。
少し不思議だけど、使い方によってはとってもかっこいいコードです。
このように4和音をマスターすると一気に音楽の世界が広がっていきます。
ぜひ学習して、色々演奏してみてください!
それではまた来月。



