こんにちは、WACCA MUSIC SCHOOLです。
今回のテーマは「地声と裏声の違い」。
日常でもよく使う言葉ですが、「実際にどんな仕組みで分かれているのか?」を説明しようとすると、意外と難しいですよね。
「高い声を出そうとすると裏返る」「地声で歌うと喉がきつい」──そんな経験は、誰にでもあると思います。
実はこの“裏返る”という現象、声帯の中で起きている小さな構造変化が関係しているんです。
声の高さを変えるたびに、声帯のどの層が動き、どの層が支えているのかが変化します。
その動き方の違いが、私たちが感じる「地声」と「裏声」の正体なのです。
今回は、声帯の仕組みと筋肉のバランスをやさしく解説しながら、地声と裏声がどのようにして生まれるのかを一緒に探っていきましょう。
最後まで読んでいただければ、今まで「なんとなく」で使っていた声の切り替えに、きっと新しい発見があるはずです。
「地声と裏声はどう違うのか」──“響きの厚み”を生む正体
同じ声なのに、あるときは太く、あるときは軽く抜ける──誰でもそんな経験があります。
私たちはそれを「地声」「裏声」と呼び分けていますが、実際にその違いを説明できる人は多くありません。
感覚的には、地声は“厚い声”、裏声は“軽い声”。でもこの「厚さ」や「軽さ」は、単なる音量や筋力ではなく、声帯のどの部分が動いているかで決まっています。
地声では声帯の奥深くまで波が届き、層全体が厚く振動しています。
そのため声に芯があり、身体の中で響くような感覚を伴います。
一方、裏声では表面の薄い層だけが動き、深い部分は支点のように動きを止めています。
つまり、声の違いとは「どの層まで波が伝わっているか」という構造上の違いなのです。
この“揺れの深さ”が変わることで、声は力強くも軽やかにも姿を変えます。
次の章では、その揺れを生み出している声帯の構造を覗いてみましょう。
声帯の中で何が起きているのか──カバーとボディの2層構造
声帯は、一枚のヒモのように見えて、実際には「カバー」と「ボディ」という2つの層でできています。
外側のカバーは、柔らかい粘膜と靭帯の層で、息の流れを受けて波のように揺れます。
このカバーの動きこそが、声の“表情”や“響きの質”をつくり出しています。
その下にあるボディは、筋肉でできたしっかりした層で、声帯全体の形と厚みを支える土台です。
ボディが働くことで声に芯が生まれ、動きが安定します。
逆にボディの支えが弱まると、カバーが過剰に動き、声は軽く頼りない印象になります。
地声ではボディまでしっかり動いて声帯全体が揺れますが、裏声ではボディが支点化し、カバーだけが動くようになります。
つまり、声帯は「カバーが波を生み、ボディがそれを支える」──この二層の協力で成り立っているのです。
では、高音になるとどうしてこのバランスが崩れ、裏声に切り替わるのでしょうか?
その鍵を握るのが、声帯を引っ張る筋肉の働きです。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!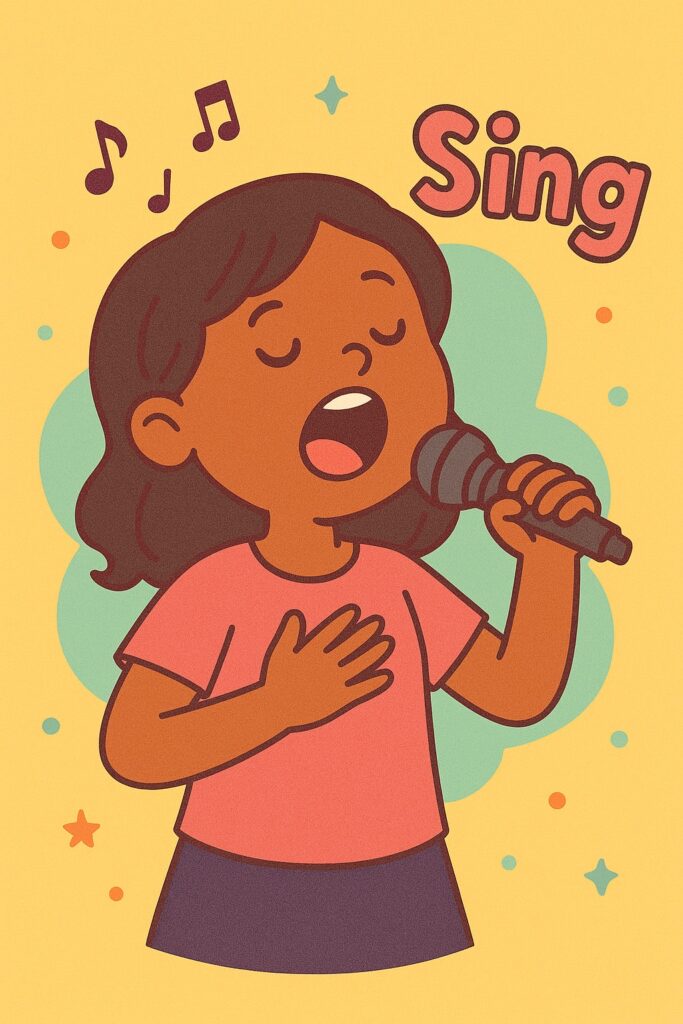
なぜ高音で裏返るのか──CTとTAのせめぎ合いで決まる声の境界
高音で声がひっくり返るのは、声帯を引っ張る力(CT)と、内側から支える力(TA)のバランスが崩れ、筋肉の弾性が失われるからです。
声帯は音が高くなるほど、前後にぐっと引き伸ばされます。このとき、外側のカバーも、内側のボディ(TA)も、まるでゴムのように張力を受けています。
CT(輪状甲状筋)は甲状軟骨を前方に倒し、声帯を長く薄くして音の高さを作り出します。対してTA(甲状披裂筋)はその引っ張りを内側から押し返し、声帯の厚みと弾力を保ちます。
この2つの筋肉は、常に“引っ張る力”と“支える力”の綱引きをしながら声帯の形を保っています。
CTが勝ちすぎると声帯はピンと張り、TAが負けてしまう。TAが優位になると今度は厚みが出すぎて、息の通り道が狭くなる。どちらも極端になった瞬間、声は自然な波を失います。
CTが優位になったとき、ボディの筋肉(TA)は“受け身の状態”になります。表面上は緊張して見えても、実際には能動的に縮む力を発揮できない――つまり「弾性を失った状態」です。
このとき、カバーは過剰に引っ張られて硬くなり、ボディは波を押し返せなくなります。結果、カバーだけが表面で波打ち、深層の動きは止まってしまいます。
高音で声が裏返る瞬間とは、引き伸ばされすぎた声帯が“動ける柔らかさ”を失い、弾性が切れてしまった状態なのです。
多くの人が「力を抜いたら裏声になる」と感じるのは、実は抜いているのではなく、CTに引っ張られすぎてTAが働けなくなっているだけなのです。
その結果、表層のカバーだけが振動し、軽くスカスカした響きになります。裏声が“軽い”のは、内部の支えが機能停止しているためです。
反対に、TAが優位になると声帯が分厚く固まり、息の流れを押し出すような地声になります。これは“支える力”が強すぎて、波を押し返す余白がなくなっている状態です。
どちらに偏っても、声帯は「動ける余白」を失ってしまうのです。
理想的なのは、CTが引っ張り、TAがほんの少しだけ抵抗しながら弾性を保っている状態です。
このわずかな拮抗があることで、声帯は伸びながらも縮もうとし、カバーとボディの間に“ズレと戻り”が生まれます。
そのとき、深層から表層まで波がなめらかに伝わり、声は裏返らずに自然に高音へ移行します。これが、いわゆるミックスボイスの正体です。
裏声や地声を分けるのは、声帯そのものではなく、その内部でどの筋肉が「動ける余白を残しているか」。
高音で声が裏返らない人は、このCTとTAの力加減を無意識に整え、“動ける状態”を保てているのです。
では、この「弾性」という働きが、どんな条件で保たれるのでしょうか。次の章では、緊張と弛緩の関係から詳しく見ていきましょう。
弾性が声を決める──緊張と弛緩のバランス
声帯がどのように振動するかを決めるのは、筋肉の強さではなく「弾性の状態」です。
弾性とは、外から力を加えられても元に戻ろうとする力のこと。ゴムのように引っ張られても、形を変えながら戻ろうとする“反発の余白”がある状態を指します。
この弾性があるからこそ、声帯はただのヒモではなく、柔らかくも芯のある音を生み出すことができるのです。
ところが、弾性は筋肉の力を入れれば入れるほど強くなるわけではありません。
むしろ、力を入れすぎると筋肉は動けなくなり、硬い板のように固定されてしまいます。
この状態では、波を伝えるどころか、空気の圧力をはね返してしまうため、声が詰まり、響きが消えます。
逆に、力を抜きすぎると今度は張力がなくなり、波を受けても押し返せず、息が抜けるような音になります。
つまり、「硬すぎても、緩すぎても、波は生まれない」のです。
声帯が最も自然に響くのは、すべての層が“動ける余白”を持っているときです。
それは、筋肉が完全にリラックスしている状態ではなく、「張りながら動ける」バランスの中にあります。
たとえば、手を軽く握ってボールを持つとき、力を入れすぎると手はこわばり、動きが止まります。
逆に、ゆるめすぎるとボールを落としてしまう。発声もこれと同じで、張りと余白の間に“支え”が生まれます。
声帯でも同様に、ボディ(TA)がほどよく働きながらも、カバーに動きを許しているとき、層同士の間に「ずれ」と「戻り」が生じ、波が連続して伝わります。
このときの声は軽やかで、息の流れに自然に乗るように鳴ります。
つまり、弾性とは「動くための張り」であり、「止めないための力」と言い換えることができます。
地声が強く響くのも、裏声が柔らかく伸びるのも、どちらも弾性が生きているからです。
違うのは、どの層がその弾性を保っているかだけで、原理はまったく同じ。
過度な緊張や弛緩が起これば、どんな声区であっても波は止まり、音は硬く、あるいは抜けてしまいます。
要するに、どの層であれ、適度な緊張感があれば弾性をおびて、過度な緊張や過度な弛緩が起これば弾性は失われる──それが声の振動を決める最も基本的なルールなのです。
弾性を感じる発声練習──裏声と地声を行き来する感覚を掴む
理論を理解したら、次は自分の声帯の弾性を“感じる”ことが大切です。
声の弾性は、目で見ることはできませんが、体の感覚として確かに存在します。
それを最もシンプルに確かめられるのが、「地声から裏声へ」「裏声から地声へ」と滑らかに行き来する練習です。
まずは小さな声で「うー」や「ねー」などの母音を使い、できるだけ力を抜いたまま低音から高音へゆっくり上がってみましょう。
途中で声がひっくり返ったり、途切れたりするポイントがあるはずです。
それは、声帯のどこかの層が弾性を失い、波が途中で止まっているサインです。
次に、その裏返るポイントの前後で息の流れを少し増やしてみてください。
喉を押さえ込まず、息に任せて声を乗せるように発声すると、波が途切れずに上までつながっていくのがわかるでしょう。
このとき、声帯の内部ではカバーとボディの間に「ズレ」と「戻り」が生まれ、弾性が保たれています。
重要なのは、声を“変えよう”とすることではなく、“波を途切れさせない”ことです。
地声をそのまま高くしようとすると、ボディが固定されて弾性を失い、波が止まります。
逆に裏声をそのまま低くしようとすると、ボディが動きすぎて支点がなくなり、波が乱れます。
この2つの境界を何度も往復し、波がなめらかに繋がる感覚を探していくことが、弾性を体で覚える最も確実な方法です。
弾性のある発声では、喉の奥に「ピンと伸びながらもしなやかに動く」ような感覚が生まれます。
息を押し出しているわけでも、喉を締めているわけでもないのに、声が遠くまで届く――それが弾性を保った声帯の働きです。
この感覚が掴めてくると、地声・裏声という区分そのものが曖昧になり、“声がひとつ”に感じられるようになります。
弾性を意識した練習は、声を強くすることではなく、自由にすることです。
どんな高さでも、どんな音色でも、声が軽やかに波の上を滑るように響く――その感覚を目指して、少しずつ自分の声の中のバランスを探っていきましょう。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
よくある質問
ここまで読んでくださった方から、よくいただく疑問をいくつかご紹介します。
声帯や筋肉の仕組みは少し難しく感じるかもしれませんが、感覚として理解できれば発声はぐっと楽になります。
トレーナーの視点から、できるだけわかりやすくお答えします。
Q. 地声と裏声の境目をなくすにはどうしたらいいですか?
境目をなくすには、どちらかの声を強くするよりも「行き来できる弾性」を育てることが大切です。
地声のまま高音に行こうとすると声帯が固定され、裏声のまま低音に行こうとすると支点が崩れます。
境目で声が切り替わるのは自然なこと。まずはその“切り替わりの瞬間”を感じ取り、少しずつ波をつなげる練習をしましょう。
Q. 裏声を鍛えると地声も強くなりますか?
はい、裏声のトレーニングは地声を安定させるうえでもとても有効です。
裏声を使うと、普段あまり動かしていないカバー層が柔軟になります。
それによって、地声の発声時にも声帯全体がしなやかに動けるようになり、結果として地声の響きや音域も広がっていきます。
Q. 力を抜くと声が弱くなってしまいます。
「力を抜く=何もしない」ではなく、「余白をつくる」と考えるのがポイントです。
声帯は完全に脱力すると息が漏れてしまいますが、ほどよい張りを保つことで弾性が生まれます。
つまり、抜くべきは“押しつける力”であって、“支える力”ではありません。呼吸の流れを感じながら、張りとゆるみのバランスを探しましょう。
Q. ミックスボイスって、結局どんな声ですか?
ミックスボイスとは、地声と裏声の中間にある“弾性が保たれた状態”のことです。
CTとTAが拮抗して働き、声帯全体に柔らかい張りが保たれているとき、深層から表層まで波が連続して伝わります。
それによって声が一体化し、地声でも裏声でもない自然な響きが生まれるのです。
このようなバランスは誰にでも育てることができます。日々の練習で少しずつ、声帯に“動ける余白”を与えていきましょう。
まとめ──声は「力」ではなく「余白」で鳴る
声をコントロールすることは、力を加えることではありません。どれだけ“動ける余白”を保てるかです。
声帯が硬直すれば波は止まり、緩みすぎれば波は消えます。声が自然に響くのは、その中間にある「弾性の余白」が保たれているときだけです。
その余白こそが、息の流れを受け止め、跳ね返し、音へと変えるためのスペースです。
地声も裏声も、本質的には“どの層がその余白を保っているか”の違いにすぎません。
地声ではボディ(TA)が、裏声ではカバーが、そしてその中間では両者が拮抗しながら弾性を支え合っています。
どんな声区であっても、動ける余裕さえ残っていれば、声は自然に響いてくれます。
発声とは、身体を固めることではなく、呼吸とともに“動ける声帯”を育てること。
焦らず、少しずつ、自分の中の声の柔軟さを取り戻していくことが、上達への近道です。
その過程の中で、あなたの声は地声でも裏声でもなく、たったひとつの“自分の声”として鳴りはじめます。
声は「力」ではなく「余白」で鳴る。
今日の発声がうまくいかなかったとしても、その“余白”がある限り、声は必ず変わっていきます。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
WACCA MUSIC SCHOOLでは、今回のテーマのように「身体の仕組みから声を理解する」ことを大切にしています。
もし自分の声の仕組みをもっと深く知りたいと感じたら、ぜひ一度レッスンで一緒に体感してみてください。
あなたの声が、もっと自由に、もっと心地よく響くようになるはずです。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

