こんにちは、WACCA MUSIC SCHOOLです。
今回は「ホイッスルボイス」について解説していきます。
普段のレッスンでも「どうやって出すの?」「苦しくならない方法は?」と質問をいただくことが多い発声法です。
この記事では、ホイッスルボイスの基本的な考え方や練習のポイント、よくある質問までまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
ホイッスルボイスとは?仕組みと特徴
ホイッスルボイスとは、人間の声の中でも最も高い音域で発声される特殊な声のことです。
笛のように鋭く澄んだ音色が特徴で、通常の裏声よりもさらに高い音域を表現できます。
マライア・キャリーやアリアナ・グランデといった世界的アーティストが使用することで知られています。
ホイッスルボイスの音域
人の声の高さは「チェストボイス(地声)」「ミックスボイス」「ヘッドボイス(裏声)」といった区分で説明されることが多いですが、C6あたりを境に、体感が大きく変わります。
それまで出していた裏声とは全く異なる鋭い音質に変化し、声が当たる位置もそれまでよりさらに高い位置になります。
C6からE6の範囲は、女性であれば普通の裏声の感覚のまま出せる人もいるので、「ヘッドボイスの最上の高さ」として説明されることもあり、普通の裏声とホイッスルボイスの転換期のような音域と言えるでしょう。
男性でこの範囲を普通の裏声で出せる人はほとんどいないので、男性にとってはこの範囲からすでに体感上はホイッスルボイスになります。
この領域は非常にコントロールが難しく、歌える人が少ないため、特別に「スーパーヘッドボイス(Super Head Voice)」と呼ばれることもあります。
F6あたりを超えるとさらに様子が変わり、スーパーヘッドボイスよりもさらに高い位置かつ細い響きの声に変化します。
もはや一般的な裏声では対応できず、全く違う仕組みで声を出さざるを得なくなります。
この特別な領域こそが「ホイッスルボイス」と呼ばれるものです。
「ホイッスル(笛)」という名前の通り、澄んで鋭い音色を持ち、まるで楽器のように聞こえるのが特徴です。
マライア・キャリーやアリアナ・グランデといった世界的な歌手がこの音域を自在に操ることで知られており、聴く人に強烈なインパクトを与える発声です。
アーティストによってはC7以上、すなわち通常の歌唱ではほとんど使われない領域まで到達する例もあり、これがホイッスルボイスの大きな特徴です。

ホイッスルボイスが出る仕組み
ホイッスルボイスの発声メカニズムは、現在も完全には解明されていません。
その大きな理由は、ホイッスルを出しているときに「喉頭蓋」という蓋のような器官が倒れてしまい、カメラでのぞいても声帯そのものが隠れてしまうからです。つまり、声帯がどう動いているのかを直接観察できないのです。
そこで研究者たちは、観察できる範囲や音響的な特徴から、いくつかの仮説を立てています。
① 声帯の先端だけが震えている説(前方声帯微小振動説)
通常の声は、声帯全体がしっかり開閉して震えることで作られます。
ところがホイッスルの場合は、声帯の前のほう、ほんのわずかな部分だけが細かく震えて音を生んでいるのではないか、という考え方です。
イメージでいえば、「大きな太鼓を全体で鳴らす」のではなく「太鼓の端のほんの少しを叩いて音を出す」ようなものです。
このため、音の高さが極端に高く、響きも鋭くなるのではないかと考えられています。
② すき間に空気が通って笛のように鳴っている説(エアリード的振動説)
もう一つの考え方は、声帯がほとんど閉じてしまい、そのすき間から空気が勢いよく抜けるときに「笛」のような仕組みで音が鳴っている、というものです。
たとえば、口笛を吹くときにほんの小さな穴から息を通すと、高く鋭い音が出ますよね。
それと同じ原理が声帯のあたりで起きているのではないか、という仮説です。
ホイッスルボイスはまだ未解明の部分も多い
このように、声帯の一部が震えているのか、それとも笛のように空気の流れで鳴っているのか、はっきりと断定はできていません。
実際にどの部分がどのように振動し、どうやって共鳴(響き)が作られているのかは、今も世界中の研究者の間で議論が続いています。
そのためホイッスルボイスは「人間の声の仕組みの中で、いまだに最大の謎のひとつ」とされており、非常に興味深い研究対象になっています。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
ホイッスルボイスの出し方と練習法
ホイッスルボイスは誰にでも簡単に出せる声ではなく、声帯や喉の使い方に特別なコツが必要です。
無理に挑戦すると喉を痛めてしまう危険もあるため、正しいステップを踏んで練習することがとても大切です。
ここではホイッスルを習得するための基本的な考え方と、段階的に進められる練習法をご紹介します。
① 吸い声を利用して感覚をつかむ
ホイッスルボイスを目指すとき、まず試してみる方法のひとつが「吸い声」を使った練習です。
吸い声とは、息を吐くのではなく吸いながら声を出す発声のことを指します。
●吸い声がなぜホイッスルボイスの練習に適しているか
声を出すとき、私たちはふつう息を吐いています。
このとき体は、限られた空気を少しでも長く持たせようと反応します。
その結果、喉が自然に締まりやすくなり、息を止める方向へと働きます。
喉が締まると声帯は厚みを増し、空気を受け流すのではなくより受け止めやすい形になります。
厚い声帯は、ギターの太い弦が低い音を鳴らすように、厚い声帯から出る声も低い音に偏りやすくなります。
一方で、息を吸うときには状況が大きく変わります。
体が優先するのは、声を出すことよりも酸素を取り込むことです。
そのため、喉を強く閉じて空気を止めるよりも、自然に空気を通そうとする方向に働きます。
この状態では、声帯を分厚く保つ必要が無いため、声帯を薄く伸ばす筋肉が動きやすくなります。
たとえば、声帯を前後に引っ張って細くする「輪状甲状筋」や、声帯を広げつつ輪状甲状筋の働きをサポートする「後輪状披裂筋」と呼ばれる筋肉です。
声帯が細く長くなり、ピンと張った状態に近づくと、高い音が出やすくなります。
これは細いギター弦を強く張ったときに高い音が鳴るのと同じ原理です。
声帯が薄く伸びることで、普段よりも楽に高音を響かせられるのです。
まとめると、息を吐いて声を出すときには体が呼気を節約しようと働くため、声帯は厚くなり低めの声が出やすい状態になります。
一方で息を吸うときには酸素を取り込むことが優先されるので、声帯は薄く伸ばされ、高い音が出やすい状態になります。
この仕組みの違いがあるからこそ、吸い声を使うとホイッスルボイスの感覚をつかみやすくなるのです。
●吸い声練習の方法とポイント
方法としては、息を吸いながらなるべく高い裏声を出そうとするだけなのですが、息を吸う量はなるべく小さくするのがポイントです。
ホイッスルボイスができるようになると分かることですが、ホイッスルボイスを出している最中は息の消費がほとんどありません。
つまり吸い声で練習する段階から、使う息の量はなるべく少なくした方がホイッスルボイスに辿り着きやすくなるのです。
また、音を当てる位置は「喉ちんこの上辺り」を意識すると良いでしょう。
吸い声の場合、上手くいくとその辺りで笛のような高音が出ます。
ぜひ試してみてください。
② 吐きでホイッスルボイスを出す方法
一度でも吸い声でホイッスルを鳴らせたなら、それは大きな一歩です。
最初は偶然のように出ただけでもかまいません。
重要なのは、その瞬間に喉や息がどんな状態になっていたかを感じ取っておくことです。
ホイッスルはとても繊細な声なので、感覚を覚えているうちに次の練習へと進めることが大切です。
次のステップでは、その吸い声の感覚を吐く発声へ移行させます。
「吸ったときに出たあの細い音を、吐くときにも同じように出せるか」という挑戦です。
いきなり上手くいかなくても気にしないでください。
大事なのは、喉を締めずに軽い感覚を保ったまま声を出すことです。
ここで意識してほしいのが、音の方向です。
声をただ出すのではなく、頬骨のあたりに向けて音を狙うようにイメージすると、スッと抜けるような音が出やすくなります。
音を前に飛ばそうとするのではなく、狙いを定めるだけで自然に音が集まるようになります。
ホイッスルを安定させるうえで欠かせないのは、息のコントロールです。
とにかく息を細くすることを心がけてください。
息を多く流そうとすると声帯に余計な圧力がかかり、鋭い音にはならずにただの裏声になってしまいます。
針の穴に糸を通すような気持ちで、息の流れをできるだけ細く、静かにコントロールするのが理想です。
ただし、このときに注意してほしいことがあります。
息を細くしようとしたときに、喉に苦しさや締め付け感を少しでも覚えたら、その時点で方向を間違えています。
ホイッスルボイスは、実際に出せると驚くほど喉が楽だからです。
苦しさがまったくない状態で、自然に高く澄んだ音が鳴るのです。
ですから、練習中に「喉がつらい」と感じたらすぐに止めてください。
無理に続けると喉を痛めてしまい、逆に習得が遠回りになります。
苦しさがなく、息がスッと抜ける感覚を大切にして繰り返していくと、次第に吐く発声でもホイッスルが安定して出せるようになります。
吸い声で得られた感覚を手がかりに、吐くときも同じ「軽さ」「細い息」「喉の楽さ」を意識していく。
これを繰り返すことが、ホイッスル習得への確実な道筋です。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!ホイッスルボイスを使う有名アーティスト
ホイッスルボイスは誰にでも出せる声ではなく、ごく限られた歌手だけがコントロールできる特別な発声です。
その希少性から、実際にステージや作品でホイッスルを披露するアーティストは、いつの時代も強い注目を集めてきました。
ここでは、世界的に知られる代表的なシンガーと、その歌声を聴ける代表曲をご紹介します。
Mariah Carey
マライア・キャリーは、ホイッスルボイスを曲の中で積極的に使う代表的なアーティストです。
「Emotions」
ライブで高音のホイッスルパートが披露されることが多く、その音色は多くの人に衝撃を与えてきました。
「BEST Whistle Notes」
彼女のさまざまなホイッスル音をまとめた映像です。
これらを聴くと、声がどのように鋭く、かつコントロールされて伸びていくかを感じられます。
Minnie Riperton
ミニー・リパートンは、1970年代にその広い音域とホイッスル使用で知られたソウル歌手です。
「Lovin’ You」
ホイッスル域を使ったパートが有名で、彼女の声の象徴的な部分となっています。
彼女の歌い方は、ホイッスルを「響きの一部」として自然に溶け込ませるスタイルが特徴的です。
Ariana Grande
アリアナ・グランデも、高音を使うポップ歌手として知られており、ホイッスルノートを披露することがあります。
「Whistle Notes 比較動画」
Mariah Carey、Ariana Grande、Minnie Riperton のホイッスルを比較できる動画です。
このような比較動画を見ると、各アーティストのホイッスル音のキャラクターの違いも感じられておもしろいです。
ホイッスルボイスを習得する際のポイント
ホイッスルボイスは、C6以降の超高音域を鳴らすために存在する特別な発声法です。
地声やミックス、ヘッドボイスをどれだけ鍛えても通常は届かない領域をカバーするためのものであり、「そこに達したら切り替えるべき専用の声区」と考えると理解しやすいでしょう。
この特性を踏まえると、ホイッスルボイスが「楽」に感じられるのは、正しく出す技術を身につけたからというよりも、その高さはもともとホイッスルボイス以外では不可能だからです。
無理にヘッドボイスで押し上げる必要がなくなる分、喉の負担が軽くなるわけです。
1. 喉に負担をかけない
ホイッスルボイスは苦しさを伴う発声ではありません。
もし出す過程で喉が締まる、息が詰まる、痛みを感じるといった状態が起きるなら、それはホイッスルボイスに入れていない証拠です。
その時点で練習を中断し、呼吸を整えてから改めて挑戦してください。
2. 息を極限まで細くする
ホイッスルボイスを出すためには「息の細さ」が何より重要です。
仕組みそのものは未解明ですが、多くのシンガーや指導者が共通して語るのは「息を極限まで細くコントロールしなければ音が続かない」という点です。
太い息をそのままぶつけると、一瞬で声が途切れたり潰れたりしてしまいます。
ストローを通すようなイメージで、最小限の空気だけを扱う感覚を練習しましょう。
3. 小さく短い音から始める
ホイッスルボイスは声量を求める発声ではありません。
むしろ「ピッ」とかすかに響く程度の小さな音から始めることが成功のコツです。
最初から長く伸ばそうとすると息のコントロールが崩れやすいため、短い音で感覚をつかんでから、徐々に持続時間を延ばすようにしてください。
4. 声区移行を意識する
ホイッスルボイスは他の声区と断絶して存在しているのではなく、ヘッドボイスを細くした先に切り替わる感覚として現れます。
意識的に「ホイッスルボイスを出そう」と力むより、ヘッドボイスを極限まで軽くしていった延長で自然に切り替える方が、安定して入りやすくなります。
5. 練習時間は短く区切る
特殊な発声法であるため、長時間続けると喉に余計な負担がかかるリスクがあります。
最初は数分で切り上げ、毎日少しずつ積み重ねる方が安全で効率的です。
短時間でも継続すれば、徐々に感覚が定着していきます。
つまり、ホイッスルボイス練習で大切なのは、
- ・喉に負担をかけない
- ・息を極限まで細くする
- ・小さく短く始める
- ・声区移行をスムーズにする
- ・短時間で積み重ねる
この5点です。
ホイッスルボイスは「高音を楽に出せる裏技」ではなく、C6以降を担うために切り替える専用の声区。
その前提を理解して練習すれば、安全に超高音域の世界へ踏み込むことができるでしょう。
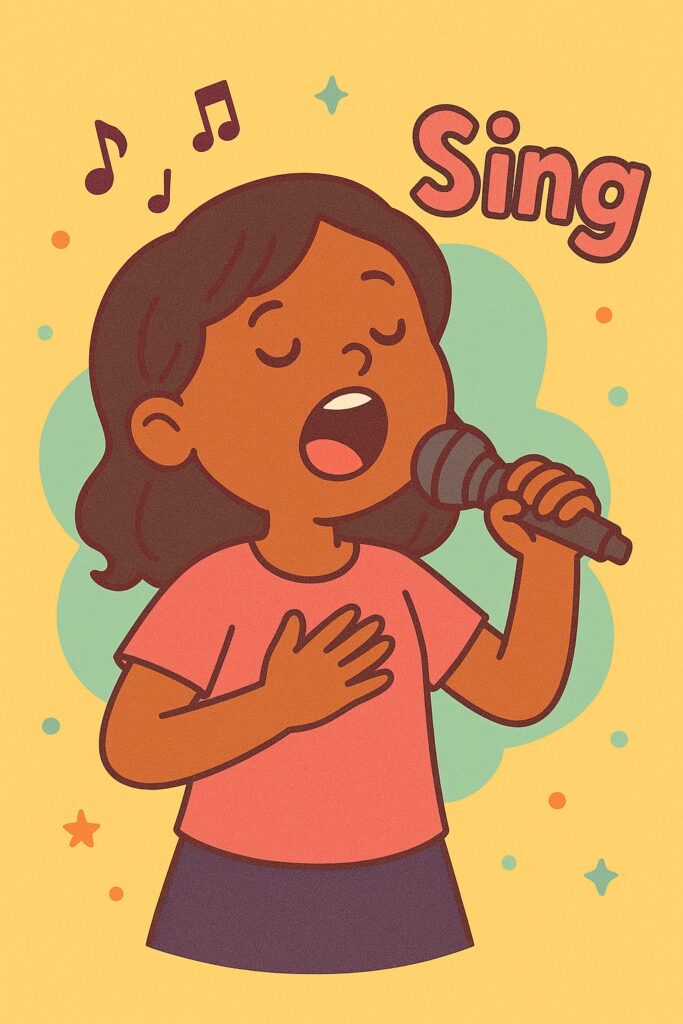
ホイッスルボイスに関するよくある質問
Q1. ホイッスルボイスは誰でも出せますか?
はい。練習を積めば誰でも出せる可能性があります。体格や声帯の形に関わらず、正しい方法で段階的に練習を重ねれば、ホイッスルボイスを再現できるようになります。
Q2. どういうときにホイッスルボイスを使うのですか?
C6以降の超高音を表現したいときに用います。通常の地声やヘッドボイスでは対応できない高さを鳴らすために存在する、専用の声区です。
Q3. 練習時間はどのくらいが適切ですか?
ホイッスルボイスは特殊な声区なので、1回の練習は数分に留めましょう。短時間でも毎日積み重ねることで、喉に負担をかけずに習得が進みます。
Q4. 苦しさを感じるのは練習不足ですか?
いいえ。ホイッスルボイスは「苦しさがゼロで成立する声」です。
息を細くする工程の段階で苦しさが出るなら、その時点で方法を間違えています。無理に続けず休憩して、アプローチを変えましょう。
Q5. 吸い声では出せるのに吐き声ではできません。なぜですか?
吸い声は息が自然に細くなるため、成功しやすい傾向があります。まずは吸いで感覚を掴み、その後で吐き声に転用していくのが効率的です。
Q6. 声がかすれてしまうのですが?
息が太すぎる可能性があります。ストローを吹くイメージで、息をさらに細く静かにしてみてください。
まとめ
ホイッスルボイスはC6以降の超高音を表現するための特別な発声法です。
練習すれば誰でも出せる可能性がありますが、無理に喉を締めつけるのではなく、息を細くコントロールしながら短時間で積み重ねることが大切です。
記事で紹介したポイントを意識して取り組めば、少しずつ成功体験が積み重なり、自分の声域の新しい扉を開けるはずです。
WACCA MUSIC SCHOOLでは、こうした特殊な発声も含めて、一人ひとりに合った練習法を丁寧にサポートしています。
興味のある方はぜひ体験レッスンで体感してみてください。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

