みなさんこんにちは!
WACCA MUSIC SCHOOLです!
「歌を歌うと、普段の喋り声のまま歌っちゃう」
「全然上手に聞こえない」
こういったお悩みをお持ちでは無いでしょうか?
今回は、喋り声ではない「歌声」とは何なのか。
また、その出し方を徹底解説していきます!
是非最後までご覧ください!
それでは行ってみましょう!
歌声とは?喋り声との違い
友達とカラオケに行った時に
「あの人の歌はサマになってるな」
「あの人は普段の喋り声のまま歌ってるな」
などと感じたことはありませんか?
歌や発声に関して詳しく無い人でも、なんとなく「歌声になっているか、そうでないか」は感じ取れてしまうものです。
歌声に聞こえる声と、普段の喋り声に聞こえてしまう声。
その差はなぜ生まれるのでしょうか。
答えは「ニュアンス」です。
ニュアンスとは
「優しい感」
「切ない感」
「元気感」
などと言った「〇〇感」で言い表せる、声から受ける印象のことです。
喋り声に聞こえてしまう歌には「ニュアンス」が欠けているのです。
ニュアンスの無い声は、なんとなくぶっきらぼうで「気を使っていない感じ」が出てしまいます。
この「気を使って歌っていない感」が、普段の喋り声で歌ってしまっているように聞こえさせているのです。
それに対して「歌声」に聞こえる声には「ニュアンス」があります。
「そっと歌っている感」
「可愛い感」
「カッコつけてる感」
などなど、挙げればキリがありませんが、何かしらのニュアンスが声に宿っていると、マイクを通したときにサマになって聞こえるのです。
これが歌声と喋り声の決定的な違いです。
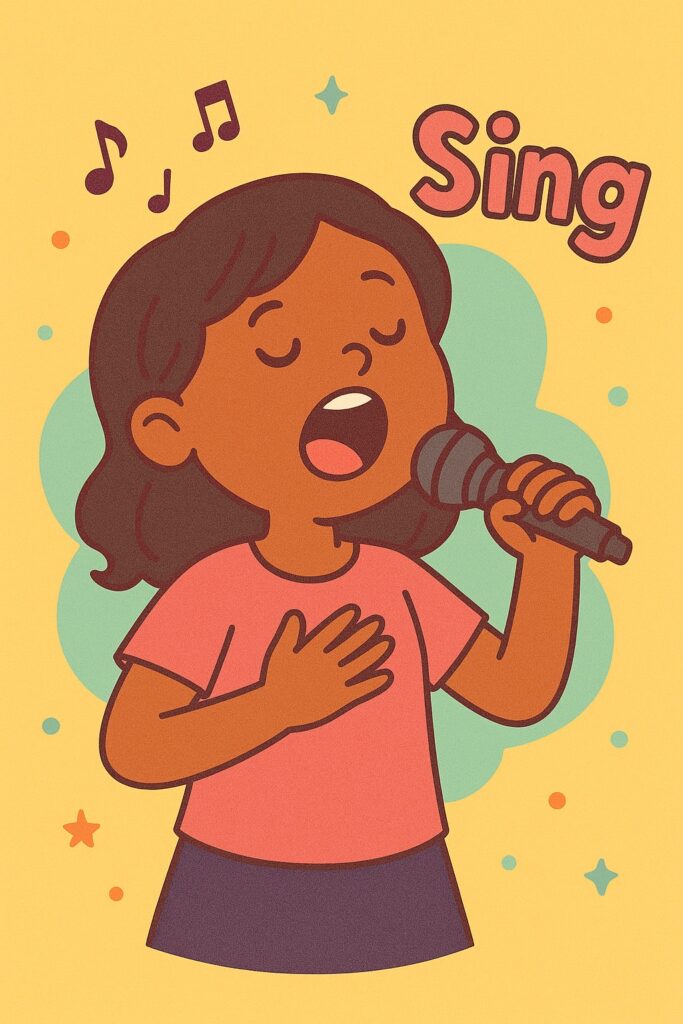
「歌声」を出すために絶対に必要なこと
声にニュアンスが宿れば「歌声」になるとお伝えしましたが、それ以前に、「歌声」を出すために絶対に必要なことが2つあります。
①歌い方の好み
一つ目は「好み」です。
それも、広く音楽に関する好みというよりかは「歌い方の好み」です。
自然と歌声で歌える人はもれなく「歌い方の好み」を持っています。
「歌い方の好み」は、それまでの人生の中で色々な歌を聴いて
「こういう歌い方良いな」
「この人の歌い方かっこいいな」
などと思ってきた積み重ねによって出来上がります。
この「歌い方の好み」があると、自分が歌う時にも無意識にその歌い方を真似しようとします。
よく「曲によって歌い方変わっちゃう」とか「無意識に本人の真似しちゃう」と言っている人がいますが、それも「この曲はこうやって歌った方がかっこいい」とか「この曲は本人みたいに歌った方が良い」と、無意識に思っているからです。
「自分の好きな歌い方を真似しようとする」ということは、何かしら気をつけながら歌っているということですよね。
何も気を付けずに歌ったら、真似なんて出来っこありません。
この「何かしら気を付けて歌っている」ことが、ニュアンスを産むのです。
先程喋り声に聞こえる歌は「気を使っていない感」があるとお伝えしましたが、まさにその反対ですよね。
「自分の好みに近づくように、一生懸命気を使って、真似しようとしている」のですから、声に何かしらのニュアンスが宿るのも当たり前だとわかってもらえるでしょうか。
喋り声で歌ってしまう人は、この「歌い方の好み」が無い場合がほとんどです。
「どんな歌が好き?」と質問しても「わからない」という答えが返ってきます。
だから、何を気を付けて歌えば良いかわからず、喋り声のまま歌ってしまうのです。
そういった人はまず「歌い方の好み」を見つけることに集中しましょう。
出来るだけ色々な音楽を聴いて「どんな歌に憧れるのか」を自問自答し続けるのです。
それによって確固たる「好み」が確立できれば、歌う時に無意識にその「好み」を再現しようとするはずなので、いつの間にか歌が喋り声では無くなっているはずです。
②最低限の喉の自由度
「歌声」を出すために絶対に必要なことの2つ目は「最低限の喉の自由度」です。
「歌い方の好み」がしっかりあって、少しでもそこに近づくように意識もしているのに、全く声に現れてこないという人ももちろんいらっしゃいます。
ニュアンスは「無意識に好みに近づけようとした際の声質の変化」によって生まれます。
真似しようと意識した結果声質が全く変わっていないのであれば、結果的には歌は喋り声のままになってしまいます。
喋り声を歌声にするためには、「意識したら多少声質変えられる」くらいの、最低限の喉の自由度が必要なのです。
「ボーカルレッスン」で歌声と話し声の違いを体感しよう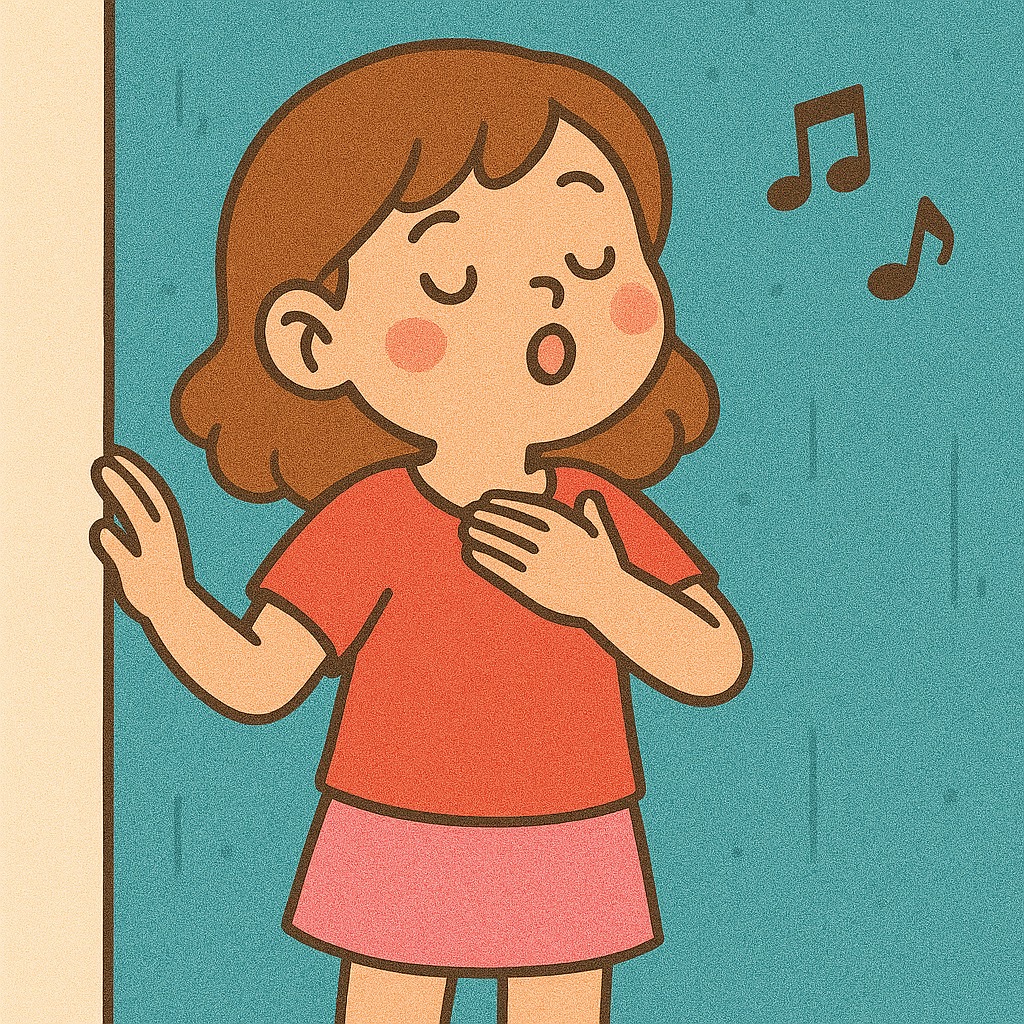
歌声を出すためのトレーニング
ここからは歌声を出すための具体的なトレーニング方法を説明していきます。
「歌い方の好み」に関しては先述の通り
①色々な音楽をたくさん聴く
②どんな歌い方に憧れるのか自問自答する
これしか方法が無いので、ここからは「歌い方の好み」はしっかりあるという前提で、意識しても声質が変えられない人に向けてのトレーニング方法を解説していきます。
①喉仏を動かしてみよう
みなさん喉仏は触れますか?
男性なら喉をさわればすぐわかるはずですし、女性も喉の前面を手のひら全体で覆いながら唾を飲み込むと、大きな骨の塊が移動するのがわかるかと思います。
それが喉仏です。
私達の声を作り出す声帯は喉仏の中に入っており、喉仏が動くと声の響き方が全く変わります。
例えば喉仏が下がると、声質はオペラ歌手のように太い音質になり、暗さや大人っぽさも付与されます。
反対に喉仏が上がれば、平べったくコミカルな印象の声になり、明るさや幼さといった印象が付与されます。
つまり、喉仏を動かせるだけで、ある程度自分がイメージした声に近づけられるようになるのです。
トレーニング方法ですが、まずはあくびをしながら声を出してみましょう。
あくびをすると必ず喉仏が下がるので、出てくる声も普段より太い音質の声が出るはずです。
その後、あくびをしながら出た声と同じ音質の声を、声真似して出してみましょう。
上手く出来ると、あくびをしなくても自然に喉仏を下げて声が出せているはずです。
喉仏を上げる方は、ポケモンのような小さくて可愛いアニメのキャラクターの声を真似するのが良いと思います。
全く似せられなくても問題ありません。
ほんの少し声が明るくなり、ほんの少し喉仏が上がるのが確認できればOKです。
それすら確認できなくても、しつこくトライしていれば絶対にできるようになります。
②息感を調整してみよう
宇多田ヒカルさん、大森元貴さん、井口理さんの歌を思い浮かべた時に、息っぽい声をよく使われる印象がありませんか?
そして息っぽい声で歌われている部分は儚さ・切なさ・優しさといったニュアンスがとてもよく表現されていますよね。
実は息感は、ニュアンスを声に込める上で「奥義」と言っても過言では無いほど、絶大な効果があります。
「とりあえず困ったら息っぽくしとけ」っていうくらい雑な考えを持つだけでも、多少喋り声感は減ります。
そのくらい、「息感」と「歌声」には密接な関係があるのです。
息感の調整は、「音程を変えずに息感を変えてみる練習」で身につけることができます。
男性A3、女性C4辺りの、出しやすい地声を出してください。
最初は思い切り息を漏らした、ウィスパーボイスのような音質で出してください。
そこから息継ぎをすることなく、音程を変えないまま徐々に音量を大きくしていきます。
すると、音量を変えているだけなのにも関わらず、息感がどんどん無くなっていくのに気がつくと思います。
実は音量というのは「息を止める動作」と密接な関わりがあり、多少息を止める動作が働かないと、パワーが上げられないようにできているのです。
逆に言えば、「パワーが出せないフォーム」のまま声を出せば、息を堰き止める動作が起こりづらくなるので、息感をしっかり残して歌うことができます。
音量が最大になると共に息感も無くなったのを確認できたら、今度はそこからゆっくり元のウィスパーボイスに戻っていきましょう。
一往復するようなイメージです。
この時に、どの辺りから「パワーが出せるフォーム」になっているのか、どこまでなら「パワーが出せないフォーム」なのかをしっかり見極めながら練習しましょう。
そうすれば、息感を出せる声の出し方と、息感が出せない声の出し方が次第にわかってきます。
慣れてきたら音程を上げてみたりしてみましょう。
特に喚声点と言われる「E4」で、滑らかにこの動作を行うのは至難の業なので、発声練習の目標にするのも良いかもしれません。
「発声基礎レッスン」で歌声の土台を作ろう!
息感のある歌い方はめちゃくちゃ難しい
声にニュアンスを乗せて「歌声」へと昇華させるには、「息感」を乗せてしまうのが1番手っ取り早いです。
しかしこの歌い方は非常に難しい点が二つあります。
「息が持たない」ことと「音量が出ない」ことです。
息感を乗せるためには「息を止める動作」を無くさなければならないので、息が抜けていってしまう上に、力も入らないので音量が出ないのです。
この問題を解決するには、横隔膜と声帯の連動が完璧に行われ、かつ声帯が効率よく振動し、それによって生まれた原音を最大限に響かせるスキルが必要です。
横隔膜で息の調整ができれば、声帯の上側にある仮声帯や喉頭蓋といった「息を堰き止められる部位」が働かなくても済むようになるので、息感がなくならないまま息を保たせることができるようになります。
また、声帯が効率よく振動し、最大限響かせられるようになれば、横隔膜によって調整された少ない呼気でも、大きなボリュームを出すことができます。
ここまでのレベルになるのは十数年単位の年月が必要になりますが、目指す価値は十分にあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 歌声と喋り声はどう違うのですか?
一番の違いは「ニュアンス」の有無です。喋り声で歌うと、ただ言葉を音に乗せているだけに聞こえます。対して歌声には「優しさ」「切なさ」「カッコよさ」などのニュアンスが宿り、聴き手に印象が残ります。
Q2. 喋り声で歌ってしまう原因は何ですか?
多くの場合は「歌い方の好み」がないことが原因です。自分の憧れる歌い方や真似したいスタイルが無いと、どこに気を配って歌えばよいのか分からず、結果的に喋り声のまま歌ってしまいます。
Q3. 歌い方の好みはどうやって見つければいいですか?
とにかく幅広い音楽を聴き、「この歌い方いいな」「この人みたいに歌いたい」と思えるものを探すことです。その積み重ねが「自分の好み」を形作り、自然と歌声にニュアンスを宿らせます。
Q4. 喋り声から歌声に変えるために、最初にやるべき練習はありますか?
おすすめは「喉仏を動かす練習」と「息感の調整」です。喉仏を上下させるだけで声質は大きく変わりますし、息感をコントロールできるとニュアンス表現の幅が広がります。まずはこの2つを取り入れるのが効果的です。
Q5. 息感を乗せた歌い方は難しいと聞きました。本当に効果はありますか?
息感を使うと「切なさ」「優しさ」といったニュアンスが一気に表現できます。ただし「息が持たない」「音量が出ない」という難しさも伴います。長期的なトレーニングが必要ですが、表現力を磨く上で非常に価値のあるスキルです。
まとめ
「歌声」と「喋り声」の違いは、声にニュアンスがあるかどうかです。歌声を出すためには、まず自分の「歌い方の好み」を見つけること、そして喉や息の使い方を工夫することが不可欠です。
喉仏を動かす練習や息感を調整するトレーニングを重ねることで、声質を自在にコントロールできるようになります。最初は難しく感じても、意識を続けるうちに必ず変化が現れます。
歌声は特別な才能ではなく、誰でも努力と工夫で習得できるものです。ぜひ日々の練習に取り入れて、自分だけの「歌声」を育てていきましょう!
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

