「歌がうまくなりたい!」と思ったとき、あなたはまず何から始めますか?
発声練習?リズムトレーニング?カラオケでひたすら歌う?
実は歌が上手くなるためには、ちょっとしたコツや意識の持ち方を変えるだけでも、大きく変化が出ます。
初心者の方でも今日から実践できる「歌が上手くなる6つのコツ」を丁寧に解説していきます。
歌が苦手な人にも、伸び悩んでいる人にも、必ずヒントが見つかる内容になっています。
1. 「しゃくり」を理解する
「しゃくり」という言葉を聞いたことはありますか?
カラオケの採点項目にもあるので割と目にする機会が多くなってきましたよね。
実はしゃくりは歌を上手く歌うためには絶対に必要なテクニックで、避けて通れません。
ここではしゃくりとは何なのか、どんな効果があるのかについて解説します。
しゃくりとは?
しゃくりとは「歌詞の一文字を2音で歌うテクニック」です。
筆者の大好きなONE OK ROCKの「Take What You Want」で説明していきたいと思います。
まず、冒頭の「過ぎ去った」の「ぎ」を聞いてください。
「ぎ」の音程はC4ですが、B3♭を一瞬出してからC4にしゃくり上げているのが聞き取れるでしょうか。
よーーく聞くと、「ぎ」という一文字を、2つの音程で歌っているのがわかりますよね。
これが「しゃくり」です。
しゃくりには
・下からしゃくり上げるパターン
・上から滑り降りてくるパターン
この2つのパターンがあります。
(※上から滑り降りてくるパターンをフォールとか言ったりするらしいですが、ややこしいので全部しゃくりで良いと思います。同じ「一文字を2音で歌う動作」なので。)
2分11秒のところの「hear」をよく聞くと、ここも2音で歌っていますね。
「hear」の本来の音程はG4なので、G4を出しておけば「hear」の部分のカラオケの採点バーは合います。
しかし、ボーカルのtakaは「hear」を一瞬A4を出してからG4に降りてきています。
これが「上から滑り降りてくるパターン」のしゃくりです。
(さっきフォールと呼ぶこともあると言いましたが、カラオケで「上から滑り降りてくるパターンのしゃくり」をやると「こぶし」が付きます。もう何が正式名称なのかわかりませんので、好きなように呼んでください笑)
しゃくりの効果
しゃくりを入れると、歌に重力感を付与することができます。
重力感とは、「溜めて、発散する感じ」「持ち上げて、落とす感じ」「振り回す(スイングする)感じ」などのことです。
「音」という目に見えないものを、扱い方だけで「重さ」があるように感じさせることができるのです。
重さを表現することができれば、あとはそれを軽くしたり重くしたり、溜めてから発散したりすることで、歌に歌詞やメロディ以上の情報を付与することができます。
迫力、グルーブ感、拍子抜け感などなど、付与できる情報はそれこそ無限大です。
しゃくりは、この「重力感」を表現する上で最も重要なテクニックです。
先程の例で言うならば、「ぎ」のところは音をそっと押し出しているような印象がありますし、「hear」のところは、ボクサーのジャブのように、素早く打ち出して戻るような印象がありますよね。
こういった印象は全て「しゃくり」によって生み出されているのです。
歌は聞き手に与える情報量が多ければ多いほど上手く聞こえるので、しゃくりをマスターして歌に重力感を付与できるように練習しましょう!
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
2. Youtubeで原曲を0.25倍速で聴く
しゃくりを練習しようにも、まずは原曲がどこをどのようにしゃくっているのかが聞き取れないといけません。
そのために必要なのか「Youtubeで原曲を0.25倍速で聴くこと」です。
再生速度が変更できるなら、Youtubeでなくても問題ありません。
とにかくゆっくり聞くことが重要なのです。
0.25倍速で聞くと、「え、こんなところでビブラートかかってるの?」とか「あれ、ここ自分が歌っているメロディと違う」という気付きがたくさん生まれます。
しゃくりに関しても、0.25倍速で聞けば明らかに2つの音程が聞こえるはずなので、それを真似して歌えば良いのです。
できれば手元にチューナーのアプリやピアノのアプリを用意して、「どの音とどの音のしゃくりなのか」ということを視覚的に確認するより良いでしょう。
歌に限らず英語のリスニングもそうですが、基本的に「話せないと聞き取れません」。
しゃくりも同様で、しゃくりができない人は普通のスピードだと絶対にしゃくりを聞き取れないので、歌が苦手な自覚がある方は、必ず0.25倍速で聞く癖を付けましょう。
3. 「息感」を意識する
これを読んでいるあなたは、自分の歌が「棒読みっぽい」ことで悩んでいたりしないでしょうか?
その原因はほぼ間違いなく「息感の欠如」です。
先程のONE OK ROCKの曲の冒頭をよく聞いてみていただきたいのですが、明らかに息っぽく優しい音質で歌っていますよね。
これは息をたくさん使って歌っているというより、「息を止めないで歌っている」から、このような歌唱ができるのです。
息が出ることと、声が出ることは別の現象です。
息を出しながら声を出すこともできれば、息を止めて声だけ出すこともできます。
(詳しくは地声を高くする方法をご覧ください)
喉で息を止めないで歌うと、声に「息感」が乗り、「ニュアンス」が宿ります。
(詳しくは歌が上手い人の特徴をご覧ください)
声に「ニュアンス」が宿れば、歌は絶対に棒読みに聞こえなくなります。
つまり、喉で息を止めないで歌うことができれば、歌は飛躍的に上手に聞こえるようになるのです。
息を止めずに流す具体的な練習方法はミックスボイスの出し方に書いてありますので、是非ご覧ください。
4. 息を止めずに高音を出す練習をする
歌を上手に歌うには「息感」が必要という話をしましたが、一曲通してずっと息感が必要な訳ではありません。
具体的に言うと、「盛り上がる部分」「声を張りたい部分」は、息感はむしろ無い方が良いです。
反対に、「目立たせたく無い部分」「静かに歌いたい部分」などは、息を止めて歌ってしまうと確実に棒読みになります。
最近のポップスでは、男性からすると高音に相当するE4やF4辺りの音程を、静かに出さないといけない場面が多くあります。
そういった曲を上手に歌いこなすためには、「息を止めずに高音を出す練習」をしていかなくてはなりません。
↑こちらのコラムなどで息を流す感覚を掴んだら、その感覚のまま地声体感を維持して音程を上げていく練習をしましょう。
最低限F4#まで息を止めずに出せれば、キーの高い最近のポップスであっても、原曲通りのニュアンスで歌えるでしょう。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!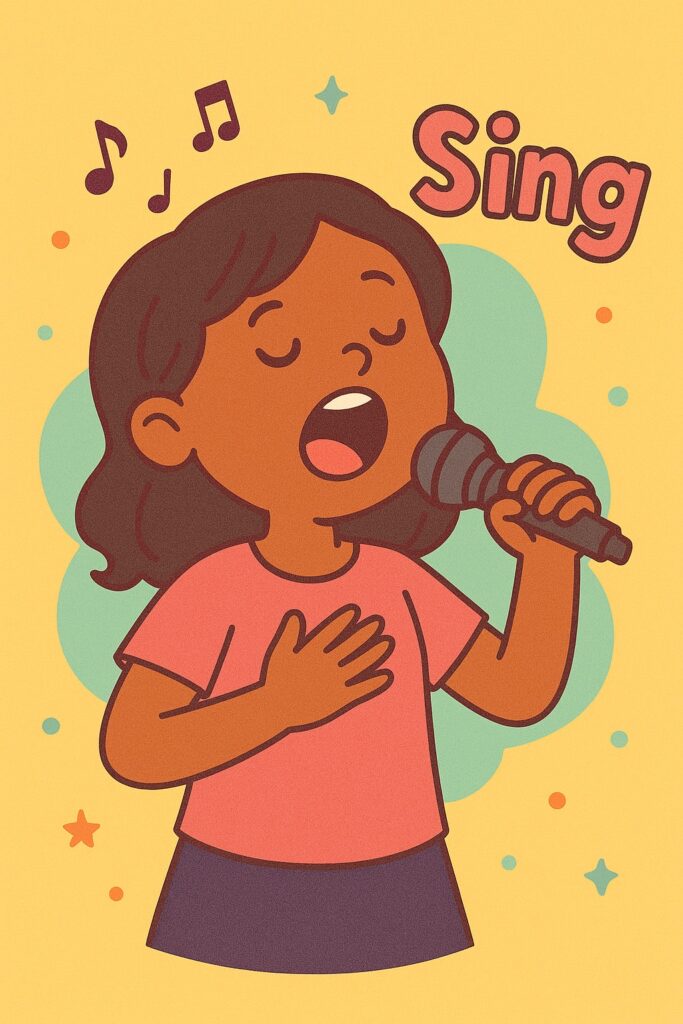
5. リズムを体で取る
日々様々な生徒さんとレッスンをさせていただく中で、「歌っているとリズムがだんだんズレていく」人は後を断ちません。
とくにCメロで急に伴奏が静かになったりすると、リズムがズレやすい傾向にあります。
この原因は「頭の中でリズムが鳴っていないこと」です。
ただ耳から入ってくるリズムに合わせるのではなく、自分でもリズムを刻んでおくことが非常に大切です。
そのために、まずは「リズムを体で取る」癖を付けましょう。
一定リズムをキープしながら、揺れてもいいし、首を動かしてもいいし、足や手で取ってもいいし、好きなようにして構いません。
とにかく体を一定のリズムで動かしておけば、急に伴奏が静かになったりしても落ち着いてリズムをキープすることができます。
いますぐにできることなので、今日から始めてみましょう。
6. 自分の歌を録音して聞く
歌が上手くなる最後のコツは「自分の歌を録音して聞くこと」です。
歌が上手くなるためには当たり前のことですが、めんどくさくてやらない人が非常に多いです。
ただ、自分の歌を録音しない人の中には「下手なのはわかるけど、何がどう下手なのかがわからない」から録音しないという人も多くいらっしゃいます。
そういった方は、今回のコラムでご紹介したポイントを中心に自分の歌を聞くようにしてください。
・原曲がしゃくっている部分を、自分もしゃくれているのか?
・原曲が優しく歌っている部分を、息を止めて歌ってしまっていないか?
・原曲が強く歌っている部分を、息を止めないで歌ってしまっていないか?
・一曲通してリズムはキープできているのか?
などなど、聞くべきポイントは音程が合っているかどうか以外にもたくさんあります。
このコラムを参考しながら、今日から自分の歌を録音して聞く癖を付けてください。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!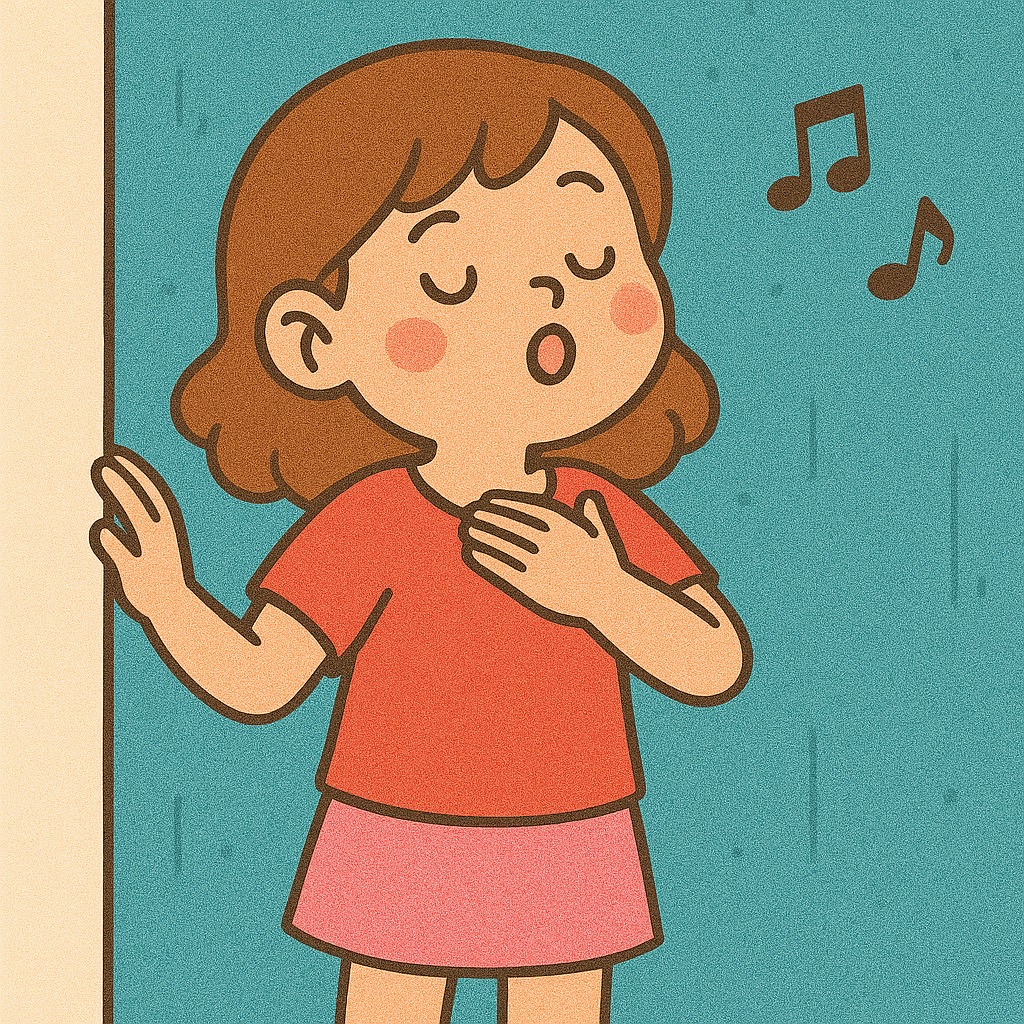
よくある質問
Q. 歌が棒読みっぽくなってしまいます。どうすれば感情がこもって聞こえるようになりますか?
「息を止めないで歌うこと」で、声にニュアンスが生まれます。
息を止めると声が平坦になり、棒読みのような印象になってしまいます。
喉で息を止めずに流しながら発声することで、音に表情がつき、聞き手に伝わる歌になります。
Q. 高い声を出そうとすると力んでしまいます。どうすれば自然に出せますか?
高音でも息を止めずに出す練習をすると、無理なく響かせることができます。
最近の曲は、静かで優しい高音が求められる場面が多くあります。
息を流す感覚を保ったまま、喉に力を入れずに地声体感で音程を上げていく練習を取り入れてみてください。
Q. 原曲を聴いても、どう歌っているのか細かいところが分かりません。
再生速度を0.25倍に落とすと、しゃくりやビブラート、音程の動きがはっきり聞き取れます。
細かなニュアンスは普通の速度では聞き取りづらいため、ゆっくり聞いて一音ずつ真似することが上達への近道です。
Q. リズムがズレてしまいがちです。耳は合っているはずなのに、なぜでしょうか?
自分の中にリズムの軸が無いと、伴奏の変化に引っ張られてズレやすくなります。
体を使ってリズムを刻むクセをつけましょう。
手拍子や足踏みなど、どんな方法でも構わないので、体でビートを取りながら歌うと安定します。
Q. いくら練習しても自分が上達している気がしません。
録音して聴き返すことで、具体的な改善点と成長が見えてきます。
自分の歌を客観的に聞く習慣がないと、「何が悪いのか」「どこが変わったのか」が分かりません。
しゃくりや息感、リズムなど、意識すべきポイントに沿って聴き直すと、課題が明確になります。
まとめ
歌が上手くなるためには、ただ闇雲に練習するのではなく、「正しい方向で」「効果的なポイントを意識して」取り組むことが重要です。
今回ご紹介した6つのコツは、どれも今日から実践できるものばかりです。
中でも「しゃくり」「息感」「録音チェック」は、変化を実感しやすく、初心者に特におすすめのテクニックです。
小さな発見と修正を積み重ねていけば、確実に歌は上達していきます。
ぜひ今日からこのコツを一つずつ実践して、自分の歌声の変化を楽しんでください。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

