みなさんこんにちは!
WACCA MUSIC SCHOOLです!!
本日は「喉を開く方法」について書いていきます!
今回はこの難解な言葉の意味を一緒に解き明かしていきましょう!
「喉を開く」とは?
「喉を開く」といえば、「お腹から声を出す」「喉を締める」などと並ぶ、ボイトレ業界の意味不明キーワードの代表選手ですよね!笑
「喉って、、、開くの?」と感じるのが正常だと思います。
もちろんプレデターやエイリアンのように喉がパカっと開くわけはありません。
ここでは「喉を開く」が具体的に何を指しているのかを説明していきます。
「喉を開く」と「声帯を開く」は違う
まず、1番陥りやすい誤解を先に解いておきます。
「喉を開く」は「声帯を開く」という意味ではありません。
声帯を開いてしまうと、声帯は振動しなくなってしまいますので、声が出なくなってしまいます。
喉の辺りにあって、「開ける」部位といえば真っ先に思いつくのが「声帯」だと思うので、このように勘違いしてしまうのも無理はありません。
「喉を開く」という言葉自体が、誤解を招く良くない表現なのだと思います。
開くのは声帯ではなく「仮声帯」
「開く」のが声帯ではないのだとしたら、一体何が開くのでしょうか。
それはズバリ「仮声帯」です。
仮声帯は(カセイタイ)と読みます。
声帯の直上に付いている、「息を堰き止めるための弁」で、声帯とは完全に別の部位です。
(詳しくは「高い声を出す方法」をご覧ください)
仮声帯は息を堰き止めるための弁なので、仮声帯が閉じれば息は止まり、仮声帯が開けば息は流れます。
つまり「喉を開く」とは「仮声帯を開いて息を流して」という意味なのです。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!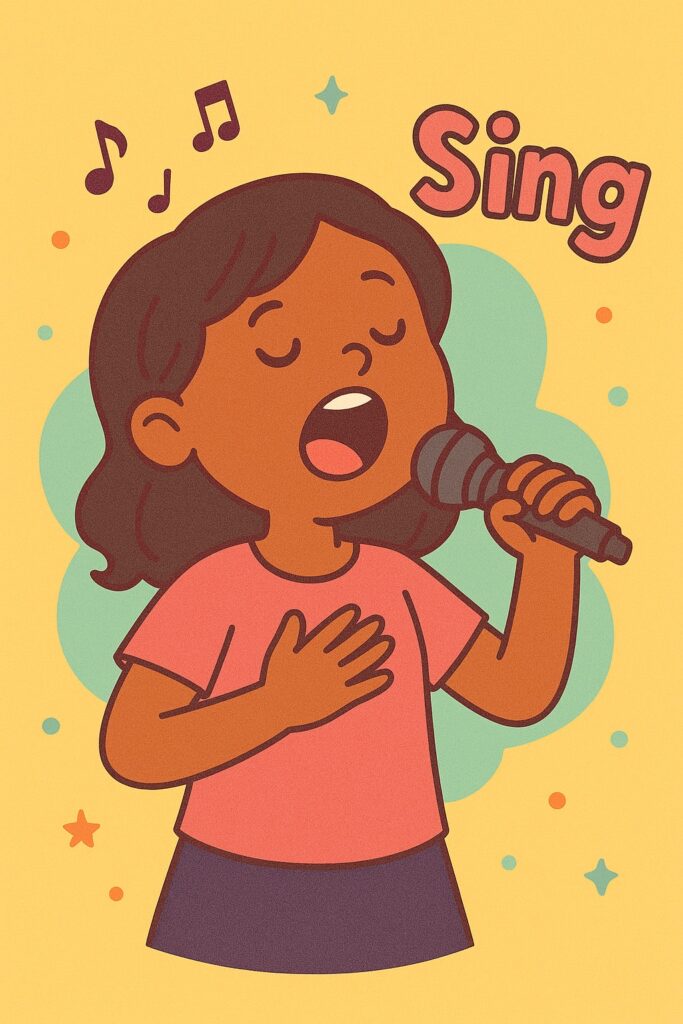
「喉を開く」メリット・必要性
なぜ「喉を開く」必要があるのでしょうか。
理由は2つです。
① 仮声帯閉鎖が「嚥下」動作を利用して行われるから
物を飲み込む動作(嚥下)を行うと、喉仏が限界まで上がり、誤嚥防止のために声帯や仮声帯など「閉められる部位」が全て閉まります。
嚥下を行うと喉仏が上がるので、逆に言えば喉仏を上げれば嚥下の際に起こる作用が呼び起こされます。
ほとんどの場合、仮声帯はこの特性を利用して閉鎖されているので、息が詰まり過ぎてしまい、息苦しさや喉締め感を産んでしまうのです。
② 息感が無くなり歌が上手に聞こえないから
嚥下を利用した行き過ぎた仮声帯閉鎖は、声から「息感」を奪い、詰まったような閉塞感のある音質にしてしまいます。
それでは歌が上手に聞こえる声ではなくなってしまうので、喉を開いて息を流す動作が必要になります。
喉を開く方法
喉を開くとは「仮声帯を開くということ」だと説明しましたね。
仮声帯は「息を堰き止める弁」なので、息を堰き止める動作と反対のことをすれば仮声帯は開き、「喉を開く」ことができると考えられます。
息を堰き止める動作の反対は「息を吐く」動作ですよね。
つまり、「息を吐く」ことと「声を出す」ことを同時に行えば、喉は自然と開くのです。
声を出すだけでは喉は開かない
「息を吐くことと声を出すことを同時に行うって、そんなの当たり前じゃない?」と思われた方もいらっしゃると思います。
その通りです。
声が出ている以上、多かれ少なかれ息は吐いています。
ただ、ここで言っている「息を吐くことと声を出すことを同時に行う」は、「息を吐くことを意識的に行いつつ、声も同時に出す」という意味です。
「声を出したら結果的に息も出ていた」は該当しません。
以下にやり方を説明します。
喉を開く方法
ほっぺを膨らませて「フー」と息を吐いてください。
ほっぺは限界までパンパンにします。
その状態で、最低5秒は息を吐き続けられるくらいの息の出方に調整してください。
それができたら、息を吐きながら「ウー」と声も出してみましょう。
この時に、息を吐く動作が止まってしまったり、上手く声が出なかったりしたらダメです。
ほっぺをパンパンにして息を吐き続けたまま、スムーズに声を乗せられるように練習してください。
上手くできない人は、声を出す時に自動的に仮声帯が閉まる癖がある可能性が高いです。
この癖を放置したまま歌を歌っていると喉が締まってくるので、この練習をして声を出しながら喉を開く癖を付けましょう。
うまくできるようになったら、そのまま口を開けて発音を「ア」にしてください。
すると、詰まったような閉塞感も、喉の締め付け感も無い、リラックスした声が出せるはずです。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
喉を開いた後の新たな問題
喉を開くことができるようになると、新たな問題が立ち塞がります。
「息が保たない」という問題です。
先述の出し方のままロングトーンをしてみると、普段の発声よりもずっと息が保ちずらいのがわかるかと思います(息が保つ人ももちろんいます)。
実は、声を出す際に仮声帯が閉じてしまっていたのは、息を保たせるためだったのです。
横隔膜で息を調整するスキルが無いと、発声の際に息が出て行き過ぎてしまうので、喉で息を止めるしか無くなってしまうのです。
これが仮声帯が閉まっていた理由です。
喉を開いて息の堰き止めを解除してしまったら、息が保たないという元々の問題に立ち戻るだけなのです。
この解決方法は、呼吸トレーニングによって横隔膜のトレーニングによって横隔膜で息の量を調整するスキルを身につけるしかありません。
つまり、本当の意味で喉を開いて歌を歌うためには、息を流すだけでなく横隔膜で息が出過ぎないように調整するスキルも必要だということです。
横隔膜のトレーニングについては腹式呼吸の方法をご覧ください!
よくある質問
Q1. 喉を開く感覚がうまく掴めません。
仮声帯を開く動作は日常生活で意識しないため、最初は分かりにくいものです。
喉が開くと、仮声帯が離れると同時に声帯も過度に分厚くなることをやめるので、声帯の質量が減ります。
そうなると、声の響きは「喉」ではなく「上顎の辺り」に浮いたような体感になります。
ほっぺを膨らませて息を吐く練習を繰り返し、息の流れを感じながら声を乗せられれば、だんだん感覚が掴めてきます。
Q2. 喉を開くと声が弱くなってしまいます。
最初は誰でもそうなります。
今までは息を堰き止めることで強い空気を声帯にぶつけて、強い音を出していたに過ぎません。
声帯筋などの筋肉が目覚めて声帯の振動効率が上がり、生まれた原音を上手に響かせられるようになれば、弱い呼気圧でも強く響かせられるようになります。
諦めずに「息が流れた発声のまま強く声を出す」ことを意識しましょう。
Q3. 会話のときも喉を開いたほうがいいですか?
その方が喉の負担は減ります。
長時間話していると声が枯れてしまったりするのは、息を堰き止めて強い呼気圧で圧迫しているのが原因です。
普段から息を流しておけば、より声帯の負担は軽減できます。
普段の会話から気をつけるのは日常生活に支障が出るので必須ではありませんが、意識するくらいならしておいても良いかもしれません。
まとめ
今回は「喉を開く」というテーマについて、その意味や必要性、そして具体的な練習法をご紹介しました。
最初は感覚が掴みにくいかもしれませんが、正しい方法で繰り返し練習することで、声の響きや発声のしやすさが格段に向上します。
あなたもぜひ日々の練習に取り入れてみてはいかがでしょうか?「喉の力み」が取れ、より自由で心地よい発声ができるようになるはずです。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

