ビブラートは、歌や楽器演奏の表現力を高めるために欠かせないテクニックです。
本記事では、ビブラートの意味・種類・出し方・練習法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
正しく理解して習得することで、あなたの歌や演奏が一段と魅力的になりますよ。
ビブラートとは?基本の意味と仕組み
ビブラート(Vibrato)とは、音を「小さく周期的に揺らす」ことで、響きや感情表現を豊かにする技法です。
イタリア語で「震える」という意味があり、声楽やポップスだけでなく、弦楽器・管楽器で使われます。
「音程が一定のリズムで変動する」のが特徴で、適切に使うと聴き手に心地よい余韻を与えます。
ビブラートの仕組み
実はビブラートは生理学的に説明することができます。
まず、みなさんの声が作られる「声帯」は、どこにあるのかご存知ですか?
正解は「喉仏の中」です!
喉仏の中の声帯が伸び縮みすることによって厚さが変化し、結果的に音が高くなったり低くなったりしているのです。
そして声帯の伸び縮みは「喉仏を形作る軟骨が傾く」ことによって引き起こされています。
もし仮に、喉仏の軟骨が「傾く→元に戻る」を繰り返せば、当然声帯も「伸びる→縮む」を繰り返して、音程も「上がる→下がる」を繰り返しますよね。
実はこれがビブラートの原理なんです。
ビブラートは、喉仏を形作る軟骨が、傾いたり、元に戻ったりを高速で繰り返すことによって引き起こされています。
より具体的に言うと、喉仏の軟骨を「斜め前下方向」に引っ張る筋肉である「輪状甲状筋」と、「斜め後ろ上方向」引っ張る「甲状咽頭筋」が、緊張と弛緩を交互に、かつ高速で繰り返すことで、喉仏の傾きが高速で変化し、ビブラートになるのです。
後述しますが、これ以外の方法でかけられたビブラートは、正確にはビブラートとは呼ばないので注意してください。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!
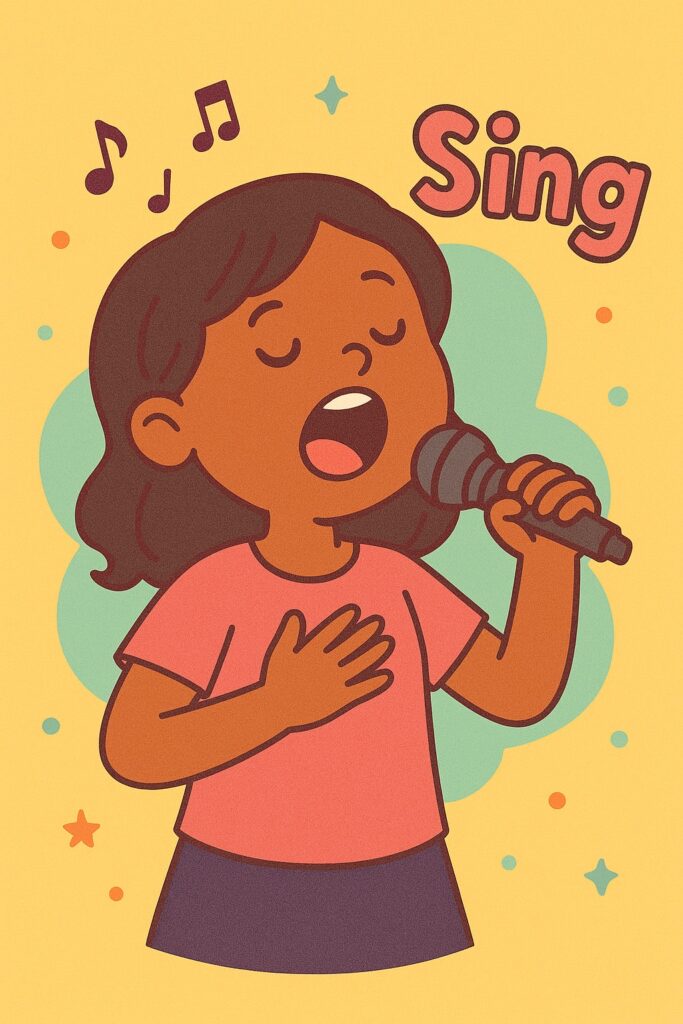
ビブラートを使う効果
ビブラートには様々な効果がありますが、意外と見落とされがちで、かつ1番本質的な効果は「歌が上手そうに聞こえる」ことでしょう。
ビブラートを使えるだけで「只者じゃない感」が出たりしますよね。
カラオケの採点機能でも、ビブラートを使うのと使わないのでは、点数に雲泥の差が出たりします。
より声楽的な効果でいうと、感情表現ができるところがビブラートの利点です。
・柔らかくリラックスした印象を与えられたり
・か細く不安定な印象を与えられたり
・しっかりと安定した印象を与えられたり
挙げればキリが無いほど、ビブラートだけで様々な印象を与えることができます。
歌の語尾は、どう処理するかによってその後の余韻が全く変わってくるので、ビブラートを使って語尾を処理できるかどうかは、歌が上手いかどうかに密接に関わってきます。
積極的に習得しましょう。
ビブラートの習得パターン
ビブラートには習得パターンが2通りあります。
すなわち
「自然に習得するか」
「練習して習得するか」
です。
細かく解説していきます。
ビブラートを自然に習得するパターン
実はビブラートは「発声のバランスが整えば勝手にかかる」と言われています。
「なんで?」と思いますよね。
先述した「ビブラートがかかる仕組み」を思い出して欲しいのですが、ビブラートは「輪状甲状筋」と「甲状咽頭筋」が交互に緊張と弛緩を繰り返すことで起こります。
この仕組みを基準に考えると、逆にビブラートがかからない状態は、「輪状甲状筋」と「甲状咽頭筋」がずっと緊張しっぱなしの状態だと考えられますよね。
筋肉がずっと緊張しっぱなしの状態は、果たして自然な状態と言えるのでしょうか。
なんとなく違いそうですよね。
例えば、足を伸ばし切った一瞬はリラックスできるスクワットを10秒間行うのと、緊張状態が延々と続く空気椅子を10秒間行うのでは、疲労感が全然違いますよね。
つまり、喉の筋肉達の目線で言えば、「ビブラートはかかってくれた方がありがたい」のです。
しかし、喉の筋力不足や、神経発達の未熟さ、呼吸の浅さなどが原因で緊張せざるを得ない状況が続いていると、喉は自然と弛緩することを忘れ、緊張状態で発声することに慣れてしまうのです。
ボイストレーニングによってこの無意識の緊張状態が無くても発声が成立するようになれば、「ビブラートが自然とかかる」というのもそこまで夢物語ではなさそうですよね。
これが自然とビブラートを習得するパターンです。
ビブラートを練習して習得するパターン
ビブラートは自然にかかるとは言ったものの、そこまでの領域に達するには数年から十数年単位のトレーニングが必要です。
そこまでビブラートはかけないで歌続けるのもあまり現実的では無いので、ビブラートの練習は少なからず必要になります。
具体的な練習方法は後述しますが、基本的な考え方は「”1秒間に6揺れ”を目指して揺らし続ける」です。
実は、ビブラートが自然にかかるようになった際の揺れの周期は決まっていて、だいたい1秒間に6回揺れる幅になります。
裏を返せば、1秒間に6回の揺れを目指して声を揺らし続けることで、発声のバランスが理想的な状態に近づくと考えられます。
そこを目指して、ロングトーンで揺らす練習を繰り返すのです。
ビブラートとは別のボイストレーニングもやりつつ、ビブラートの練習もすれば、最速でビブラート習得に近づけます。
ビブラートの練習で気をつけるべきポイント
ビブラートを練習する方法は先ほどお伝えした通りです。
ここからは、ビブラートの練習をする際に意識するべきポイントをお伝えしていきます!
ポイント①腹式呼吸
ビブラートは筋肉を弛緩させられないとかからないので、リラックスして発声できる体制を整えていかなくてはなりません。
その上で絶対に必要なことは、腹式呼吸です。
胸式呼吸の場合、首や肩の筋肉を使って胸郭を持ち上げて呼吸するので、首や肩に常に緊張感がある状態になっています。
普段の呼吸が腹式呼吸になっていると、歌唱中でも首や肩の筋肉の緊張をリセットできる瞬間が作れるので、苦しさが大幅に軽減されます。
ビブラートの練習でも、腹式呼吸になっているかどうか、首や肩で呼吸をしていないかどうか気にしてください。
ポイント②息を流す
喉には声帯とは別に、息の流れ調整する機能を持つ「仮声帯」や「喉頭蓋」といった器官が付いています。
声帯は上方向に向かって付いているため、音を鳴らすのには適していても、息の流れを調整するのには不向きです。
「仮声帯」や「喉頭蓋」を閉じていくことで、「声は出ているが息は止まっている(止まっていると感じられるくらい、息が出る量が少ない)」状態を作ることができます。
しかし、仮声帯や喉頭蓋を閉じていくということは、腹圧によって生み出される強大な空気圧をしっかりと受け止める形になるため、脱力とは真逆の方向へ作用します。
そのため、ビブラートの練習では息を止めずに、流すことを意識してください。
ストローを水に付けてブクブクしながら声を出すなどの、「息を吐きながら声を出す」動作を練習すると、息が流れる感覚がわかってきます。
息を止める癖がある人がストローの練習をすると、声を入れた瞬間にブクブクの泡の量が減ってしまいます。
息の流れは変わらないまま、声だけを乗せられるように練習してください。
ポイント③横隔膜の支え
ここまでの流れを整理すると、腹式呼吸により首や肩を使わずに吸気し、息を流して発声し、1秒間に6揺れを目指して声を揺らす練習をしていくことで、ビブラート習得に近づけるという内容でした。
ここで必ず行き当たる問題が「息が続かない」です。
これはいわゆる「横隔膜の支え」によって克服していきます。
「横隔膜の支え」とは、息を吐く際に、横隔膜の緊張感を保ったまま息を吐いていくことを表します。
そうすることで、横隔膜が上がるスピードがゆっくりになり、「小さく息を吐いていくこと」が可能になります。
声帯は2cmほどの小さなヒダで、強い空気圧を受け止められるようにはできていません。
そのため、横隔膜の支えによって声帯が1番振動しやすい呼気量に調整し、息を堰き止めることなく発声していくのが、発声の最も基本的かつ理想的な形です。
ビブラートの練習も、横隔膜の支えを意識して、息を強く吐きすぎないように気をつけながら練習してください。
「パパパパパ」と高速で連打しながら息を吐いていくと、「喉で息を止めていないのに、あまり息が出ていかない」という体感を感じられるので、横隔膜の支えを感じる近道になります。
東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

ビブラートに関するよくある質問(Q&A)
Q. ビブラートは誰でも出せるようになりますか?
はい。
誰でも習得可能です。
とにかく発声をリラックスして行えるように、息を止めなくても発声できる土台を整えていくことが重要です。
Q. ビブラートはどれくらいの幅が理想ですか?
曲やジャンルによって変わりますが、声楽的に正しいとされているのは1秒間に6揺れの幅です。
Q. ビブラートは常にかけるべきですか?
いいえ、必要に応じて使い分けるのが重要です。
使いすぎるとくどくなる恐れもあるので、楽曲の雰囲気に合わせて使い分けましょう。
まとめ:ビブラートとは?正しく理解して表現力を高めよう
ビブラートは、音を揺らして響きを豊かにする大切なテクニックです。
歌や演奏に取り入れることで、表現力が格段に上がります。
今回紹介した練習法やポイントを参考に、ぜひチャレンジしてみてください。
習得までの過程も楽しみながら、あなたの音楽をより魅力的にしていきましょう!
それでは!


