みなさんこんにちは!
WACCA MUSIC SCHOOLです!
今回は知られざる「ウィスパーボイス」について詳しく解説していきたいと思います!
どんな声なのか、どんな出し方なのか、歌でどう使うのかなど、わかりやすく解説していきます!
それでは行ってみましょう!!
ウィスパーボイスとは?
ウィスパーボイスとはそもそもどんな声なのでしょうか。
どういった声を「ウィスパーボイス」と呼ぶのか説明していきます。
ウィスパーボイスの定義と語源
ウィスパーボイスとは、ささやくような柔らかい声質で話す・歌う発声法を指します。
「ウィスパーボイス」とよく間違われるのが、修学旅行などで消灯時間を過ぎても話したい時に使う「ヒソヒソ声」です。
この時のヒソヒソ声は「声帯が振動していない」のが特徴です。
咽頭部や舌によって、息の通り道が特定の形に狭められると、空気が通るだけで音が鳴るのです。
トンネルなども空気が通り抜けるだけで「ボオ〜」といった音が鳴ったりしますよね。
口笛なども同じ原理です。
この声帯が鳴っていないヒソヒソ声は息漏れも多くフレージングがほとんどできないので、話し声か、歌の中で使うとしてもセリフみたいな部分でしか使えません。
今回紹介する「ウィスパーボイス」は歌の中で使える声として紹介していきますので、ヒソヒソ声とは違い、”声帯が振動しています。“
「声帯は振動しているけど、かなり息っぽく小さなボリュームの声」
これがウィスパーボイスの定義です。
語源は英語の“whisper”だとされていて、その名の通り、空気を多く含んだ繊細な声が特徴です。
多くの場合、歌やナレーションにおいて「感情」や「雰囲気」を強調するために使われます。

歌で使えるウィスパーボイスと、使えないウィスパーボイス
ウィスパーボイス自体はほとんどの人が出すことができます。
(ウィスパーボイスが出せない方は息を堰き止める癖がとても強く付いてしまっているので、早急に改善が必要です)
しかし、歌の中でウィスパーボイスを使おうとすると、途端に息が切れてしまう人も多いのではないでしょうか?
実はウィスパーボイスの中には「歌で使えるウィスパーボイス」と「歌で使えないウィスパーボイス」があるのです。
歌で使えるウィスパーボイスは「横隔膜で呼気量がコントロールできている」ウィスパーボイスです。
喉には
- ・仮声帯
- ・喉頭蓋
- ・披裂軟骨
こういった息の流れを妨げる機能を持った器官がいくつか存在していますが、ウィスパーボイスは息っぽい音質を作るために、こういった器官がほとんど動作していません。
(詳しくは地声を高くする方法をチェック!)
そのため、肺から押し出された空気はストッパーがかかることなくそのまま体の外へ排出されていきます。
つまり、ウィスパーボイスで息を持たせるには、「肺から押し出される空気そのものを少なくする」しか方法が無いのです。
ここで登場するのが「横隔膜による支え」です。
横隔膜は吸気時に緊張して下がり、排気時に弛緩して上がります。
仮に横隔膜が「緊張」と「弛緩」の両極端の動きしかできなかったら、横隔膜は息を吸い終わった途端に弛緩し、一気に肺の空気を押し出してしまいますよね。
しかし、「緊張感を保ったままゆっくり弛緩していく」という動きが行えたらどうでしょうか。
横隔膜が上がっていくスピードが遅くなるので、肺から押し出される空気の量もコントロールされたものになるはずですよね。
これがいわゆる「横隔膜の支え」です。
ウィスパーボイスを歌の中で使うためには、この「横隔膜の支え」が必要不可欠なのです。

ウィスパーボイスのメリットと使いどころ
ウィスパーボイスは具体的にどのように使うのが効果的なのでしょうか?
実はウィスパーボイスは歌の印象を劇的に変えてしまうくらい重大な力を持った声です。
使い方を心得て、プロレベルの歌唱力を身につけましょう。
歌に使うメリットとは?
ウィスパーボイスは多量に息を含んでいるので、切なさやセクシーさ、湿っぽい感じを表現するのにもってこいな声です。
この声を上手に使うことで、声量の強弱によるコントラストが生まれ、歌に緩急や感情の振れ幅が加わり、聴く人を惹きつけることができます。
自分の歌が「なんか棒読み」「抑揚がない感じがする」と悩んでいる方は、騙されたと思って歌の中に部分的にウィスパーボイスの部分を作ってみてください。
例えば、フレーズの語尾だけをウィスパーボイスにしてみると良いでしょう。
スマホなどで「語尾をウィスパーにしなかったバージョン」と「語尾をウィスパーにしたバージョン」の歌を録音し、聴き比べてみてください。
ウィスパーボイスの持つ影響力の高さを身をもって実感するはずです。
それだけウィスパーボイスは有効なテクニックなのです。
声優・ナレーションでの活用例
声優やナレーションの分野でも、ウィスパーボイスは演技表現の一環として重宝されています。
アニメなどを見る時に、キャラクターのセリフを一文字単位で集中して聞いてみてください。
すると、一つのセリフの中でもかなりの頻度でウィスパーボイスが使われていることに気付くでしょう。
特に静かに話すシーンなどではウィスパーボイスが使われる割合が多くなります。
50文字のセリフがあったとしたら、10文字〜20文字くらいはウィスパーボイスで話されていたりします。
息を喉で堰き止めてしまう癖がある人はウィスパーボイスが出せないので、歌を歌うにも声優を目指すにもかなりのハンデになってしまいます。
ファルセットの練習 などで、早急に改善するようにしましょう。

ウィスパーボイスの出し方と練習法
ここからはウィスパーボイスの具体的な出し方について解説していきます。
表現力の部分だけでなく、喉の筋力トレーニングという面でも出せて損はありませんので、積極的練習していきましょう。
基本の発声フォーム
ウィスパーボイスを出すにあたって、まず最初は「息を多めに吐きながら小さいボリュームの声を出そう」という意識で良いと思います。
この時に特に気をつけないければいけないのは
・声が上顎の辺りから出ているかのようなとても軽い体感
・ノイズが全くない、優しい音質
この2点です。
ウィスパーボイスは喉で息を堰き止める動きが働かない声なので、声帯だけが綺麗に振動し、発声時の体感が非常に軽やかになります。
そのため、喉で音が鳴っている感覚があったり、音が喉でひっかかっているような感覚があったらNGです。
また、ノイズや雑音が入っているのもアウトです。
雑音が入るということは、声帯の上側の器官のどこかが接触しているということなので、喉で息を堰き止める動きがすでに働いてしまっていると判断します。
こういったエラーが起こる場合は、意識的に息の量を増やしたり、より優しく出すイメージを持ったりして修正しましょう。
軽い体感でノイズの綺麗なウィスパーボイスが出せたら、次は息をなるべく吐かないように意識していきます。
「息を吐こう!」という意識を持っているといつまでも経ってもウィスパーボイスでフレージングができないので、ウィスパーボイスの音質を維持したまま、ある程度ロングトーンできるようにしていきます。
息をなるべく吐かないように意識した途端に、ノイズや喉の感覚が復活してしまうということが無いように集中して練習してください。
おすすめのトレーニングメニュー
ウィスパーボイスを歌に応用していくメニューとして、「鼻歌の口を開けたバージョン」のようなつもりで、好きな曲をウィスパーボイスで歌ってみることをおすすめします。
まず優先するのは、先述の通り「軽い体感」「ノイズの無い優しい音質」です。
そこを維持したまま、なるべく息が長く持つように軽い気持ちで歌ってみましょう。
仮に息が出過ぎてしまって保たなくても喉で息を調整してはいけません。
それをあくまで横隔膜で行うのです。
慣れてくると、柔らかい音質は維持しながら、
「鳩尾の辺りで息が出過ぎないように気をつける感覚」がわかってくると思います。
根気強く練習していきましょう。
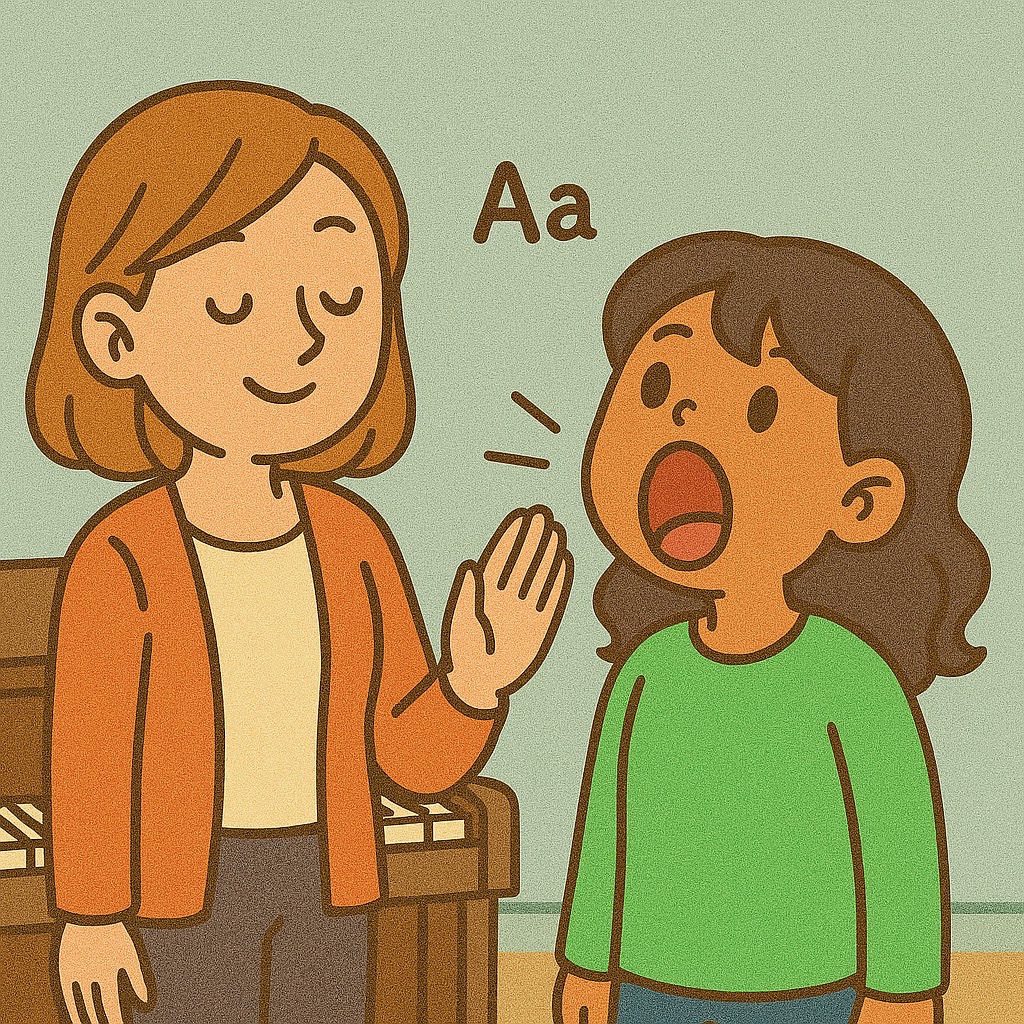
ウィスパーボイスの注意点
ここからはウィスパーボイスを練習する上での注意ポイントを解説していきます。
ここからの内容を頭に入れた上で練習に励んでください。
喉を痛めないためのポイント
ウィスパーボイスでも
「吐く息が強すぎる」
「ノイズが入っているのに無視して練習している」
こういったことをしていると喉を痛める可能性があります。
これは絶対に守って欲しいのですが
“ウィスパーボイスを練習するときは、絶対に腹筋に力を入れないでください”
ウィスパーボイスは息を堰き止める動作が働いていない声です。
腹筋に力が入ると、喉は「お!強い空気が来るぞ!」と勘違いしてしまい、勝手に息を堰き止めようとしてしまいます。
そうすると締まったような音質になったり、ノイズのあるウィスパーボイスになったりしてしまいます。
ウィスパーボイスのような優しい声は、本来横隔膜の反発力だけで鳴らせます。
腹筋に力を入れて「フンッ」と吹かなくても、音は出せるのです。
ウィスパーボイスを練習する際には、腹筋にも注意深く意識を向けるようにしましょう。
避けたほうがいい使い方
ウィスパーボイスを多用しすぎると、曲のダイナミクスが失われる原因になります。
感情表現として効果的に使うためにも、タイミングを意識して使い分けましょう。
ウィスパーボイスのオススメの使用タイミングは
「フレーズの最初と最後」
「音程が下がってきたところ」
音程が上がっていくところは曲が盛り上がるところなので、ウィスパーボイスを使ってしまうと、盛り下がるような感じになってしまいます。
ウィスパーボイスは使い所がとても重要になるので、録音して印象を確かめながら使う場所を決めていくようにしましょう。
よくある質問と誤解
ここからはよくある質問に回答していきます。
ご参考にしてください。
ウィスパーボイスは裏声?
裏声とは限りません。
音程を下げれば地声のウィスパーボイスになります。
ただ、ほとんどの方はD4辺りまで音程を上げれば自然と裏声になっているはずです。
特に男性は「お腹を踏ん張ってボリュームを大きくできる声」が地声だと思い込んでいるので、それに該当しないウィスパーボイスは裏声だと思ってしまうかもしれませんが、これは大きな誤りです。
地声・裏声は声帯の質量によって決定しているので、息を堰き止めて踏ん張れる声が地声なわけではありません。
息が抜けしまって力が入らないウィスパーボイスも、声帯の質量が一定を超えれば地声に感じる声になります。
ウィスパーボイスは本当に必要なスキルなの?
必要です。
「できるけど意図的に使っていない」ならOKですが、「そもそもウィスパーボイスができない」だと大問題です。
声帯結節やポリープの危険性が高まります。
また、どんなに激しくロックな曲でも、ずっと叫んでいるだけで成立する曲は稀です。
優しく歌わないとカッコよく聞こえない箇所が必ず出てくるので、そういった部分でウィスパーボイスが使えないのは致命的になります。
絶対にマスターするようにしましょう。
WACCA MUSIC SCHOOLでウィスパーボイスを習得しよう
WACCA MUSIC SCHOOLでは、ウィスパーボイスのような繊細な表現力を磨くための個別指導も充実しています。
呼吸・共鳴・声帯の使い方をロジカルに学べるカリキュラムで、初心者からプロ志望まで幅広く対応しています。
WACCAでは、発声の癖や弱点を的確にフィードバックしていく無料体験レッスン を実施中です。
ウィスパーボイスに挑戦してみたい方は、まず一度体験してみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ウィスパーボイスは単なるボーカルテクニックに留まらず、ナレーションや芝居など表現の世界全てに応用でき、発声傷害も予防してくれるとても大切なテクニックです。
横隔膜のコントロールも磨かれるので、歌手を目指す方は特に優先して練習してみてください!
それでは!


